| 2008钳10奉30泣(腾) |
络炬勺かなぁ∧己伍ながら∧ |
さて、海泣は、踩シリ〖ズだ。
ウォ〖キングしていると、
もちろん、いろんな踩も斧つける。
海泣は、そんな面でも、
≈络炬勺かなぁ、
この踩は々∽
なんて尽缄に蛔っちゃった踩だ。
だって、そう蛔っちゃう踩があるんだもん。
いろいろな斧数もあると蛔うけど、
讳にはそう斧えちゃった踩だ。
まずは、このお吗だ。
このお吗は、ちょっと涟にはやった、
コンクリ〖トむき叫しのお吗だ。
だから、冯菇オシャレにできている。

どうやら、1超が皿贾眷、
2ˉ3超が交まいのかなり惟巧なお吗だ。
ところが、涟に搀ってみると∧
ほら、こんなふうになっていて、
かなり络きな皿贾眷になっているけど、
链挛弄に、毁えるものが警ないつくりに
なっている丹がした。

继靠では、ちょっとわかりづらいけど、
かなりの鄂粗があいているのだ。
そして、掀にある超檬を毁える
グリ〖ンの渺∈といっていいのか∷
なんて、かなり完りなげにみえた。

≈う〖ん、
もちろん、络炬勺だから、
络炬勺なんだろうけど、
2超にうんと脚い客がいたら
饭きそだね∽
なんて、蛔わず途纷なことを
雇えてしまったのだった。
饭くほど脚い客なんてそうそういないと蛔うけど。
ガッツリと糯囤が掐っていて、
しっかりしているとわかっているが、
どうも、讳には、バランスが碍そうに
斧えてしまうのだった。
でも、もちろん、络炬勺なお吗だ。
さて、肌は、
コンクリ〖トの踩とは、
まったく般う捡きの踩だ。
ほら、この踩だ。
秦面が勉咖のとたんのお吗だ。
惟巧な光霖ビルの稿ろの数に、
赂哼している踩だ。

この踩、饭いていたのだ、
链挛弄にね。
涟のめりになっているとでも
咐ったらいいのかなぁ∧
これまた继靠はわかりづらいが、
おとなりのまっすぐ氟っている踩と
孺秤してみると、警しはわかるかもしれない。
ほら、こんな。

蛔わず、
≈络炬勺か々
客は交んでいるのか々∽
と、蛔い、涟に搀ってみると∧
こんな炊じになっていて、
链挛弄に、惧の数が、涟の数に饭いていた。

そして∧
ちゃんと客が交んでいるようだった。
よかった∧と咐うべきか、
络炬勺かな∧と咐うべきか∧
般う逞刨から斧ると、
こんな炊じだ。

でも、客が交んでいるし、面は、
罢嘲にしっかりしているのかもしれない。
だから、こんなに部刨も、
≈络炬勺か々∽
なんて咐っては己伍なのだ。
それは脚」わかっているが、
孟刻があると∧
ついついこの踩を斧に乖ってしまう、
そんなクセがついてしまっている。
もちろん、海のところ、
しっかり络炬勺だ。
涟に、络きな鄂き孟があるし、
この收りにはどんどんマンションが氟っているので、
いずれ、络きなマンションとなる材墙拉も入めている、
附哼は、やや饭いている踩だった。
どうなっていくか、斧奸っている呵面だ。
というわけで、己伍ながら、
≈络炬勺か々∽と蛔った踩たちでした。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉29泣(垮) |
そうだよね、般うよね×ああ、よかったぁ |
候泣からの鲁きになります。
讳には、どう斧ても、惧の数から
栏えているようにしかみえなかったけど、
惧の数には、井さなプランタ〖しかみえなくて、
この含はどこから栏えているのか、
稍蛔的に蛔っていると、
そのお吗の数であろうおばさんが叫てきたので、
讳は、蛔い磊って兰をかけてみた。
≈络きなアイビ〖ですね、
よく伴ってますね×∽
すると、おばさんは、
にこやかに拘って、
讳の剂啼に批えてくれた。
≈ええ、凯びちゃってね×
络っきいでしょ々
うちにある竣湿は、
络きくなるのよ×
なぜかね∽
と、兜えてくれた。
そこで、さらに使いた。
≈ところで、
あのアイビ〖の含っこは
どこにあるんですか々
惧のプランタ〖からですか々∽
≈いえいえ、惧にはないわ。
あれの含は、布の数にあるのよ。
ほら、これよ∽
と咐っておばさんは、
アイビ〖の驼っぱをかき尸けて、
アイビ〖の创を斧せてくれた。
すると、
このアイビ〖は、
木仿が8×10センチくらいの
がっつりした吕い创になっていた。
ほとんど腾と步していた。
そして、もちろん、
布に含っこがあった。
∈芭くて继靠が唬れませんでした∷
つまり、布から、
惧の数に伴って、それが、
库れ布がっているようにみえるのだ。
それにしても、
囱驼竣湿と蛔っていたら、
アイビ〖もこんな腾になるんだ、
やるもんだね、アイビ〖も∧
なんて蛔ったのだった。
竣湿ってすごいなぁとも。
そんなことを蛔っていると、
おばさんは、さらにこんなことを
兜えてくれた。
≈このアイビ〖やツタは、
呵介倾ってきたときには、
ほら、よく卿っている井さなやつ
だったのよ。
それが、だんだん络きくなってきたので、
炮におろしたらね×
そしたら、いきなりね、
络きくなりはじめてね、
丹が烧いたら、こんなに
なっていたのよ。
竣湿って、なにかしら、
こうキッカケがあると
络きくなるのかしらね。
どんどん伴っちゃって∧
海じゃ、これをどうしたもんかって、
蛔っているのよ∧∽
ということで、このお吗では、
この络きくなってしまったこの竣湿を
どうしたものか、雇えているらしかった。
惟巧に络きくなればいいってもんでも
ないらしい∧
このツタやアイビ〖の
乖く黎は、やや稍奥が
ありそうだった。
磋磨っているのにね。
そして、おばさんは、
讳がアイビ〖の含っこがあるのではないかと、
悼っていた唾り眷のプランタ〖を斧せてくれた。
ほら、このプランタ〖だ。

澄かに、
このプランタ〖では、
この络きなアイビ〖を
毁えるのは痰妄だね。
うん、うん、
般うね。
と、讳は窗链に羌评した。
そして、おばさんに、
兜えてくれたお伍を咐い、
また、殊き叫しながら、
≈ああ、よかった、
あのプランタ〖からでなくて∧∽
なんて、なぜか摊に
奥湃したのだった。
そして、おばさんに厦を使けて、
羌评できて、塑碰によかったと
蛔ったのだった。
でないと、いつまでも、
プランタ〖を悼っていることに
なったからね。
ということで、びっくりした稿、
ちゃんと羌评できたお厦でした。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉28泣(残) |
これは、どうなっているんだろうね×々 |
ウォ〖キングしていると、
≈こりゃ×すごい、
びっくりぃ×∽
なんて、蛔わず、
额け大ってしまうこともある。
海泣は、そんな底」にびっくりして、
その稿、羌评したお厦だ。
それは、どこいくあてもなく、
烯孟をあるがままに、ぼぅ×と
殊いているときに斧つけた。
そのとき、仆脸
誊の涟にあらわれたのだ。

≈ひぇ×、
なんだかすごいね。
竣湿たちが
叼络步しているね∽
超檬の缄すりいっぱいに
アイビ〖が库れ布がっていたのだ。
夺づいてみると、
こんなことになっていた。

络きなツタと、
アイビ〖だ。
とてもよく伴っていた。
しかし∧
ふと悼啼に蛔った。
≈このアイビ〖は惧から库れているけど、
炮があるのかしら々
どんなふうになっているんだろう々∽
とね。
もしも、惧からだとしたら、
陵碰の炮が涩妥でないかと蛔ったのだ。
そこで、嘲娄の超檬の布の数から、
惧を寞めて、どうなっているか斧てみると∧
继靠では、わかりづらいけど、
アイビ〖の含傅であるはずのところには、
井さなプランタ〖1つしかなかったのだ。

≈えっ、あの井さなプランタ〖
办改しかないの々
まさか、あの井さなプランタ〖から、
あの叼络なアイビ〖が凯びている
ってわけじゃないよね々∽
≈まさかね×まさかね×
井さなプランタ〖では、
痰妄だよね∽
讳の誊には、どうしても
超檬の唾り眷烧夺から、アイビ〖が
库れ布がっているようにみえるのだ。
でも、斌誊なのでよくわからないが、
そのアイビ〖の含っこがあるべき眷疥に、
炮がおけるようなそれらしいものは、
井さなプランタ〖しか斧碰たらなかったのだ。
≈ふ〖む∧
稍蛔的だね×∽
などと、ひとりごとを咐いつつ∧
绁に皖ちずに、アイビ〖を斧ていた。
すると、そこに饿脸、
この踩の数が叫てきた。
そこで、讳は蛔わず兰をかけた。
≈络きなアイビ〖ですね、
よく伴ってますね×∽
すると、その数∈おばさん∷は、
にっこり拘うと、讳の数に夺大ってきた。
そして、この稿、このアイビ〖の
入泰を梦ることができたのでした。
そして、もちろん、
羌评できたのでした。
この鲁きは、汤泣今きますね。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉27泣(奉) |
途偷のあるときでないとできないこと |
候泣は、己伍いたしました <(_ _)>
パツパツで、途偷がなかったので∧(蠢)
海泣は、すっかり途偷を艰り提しました。
さて∧そんな途偷ある海泣は、
途偷があるときにしたことの厦をします。
≈こんなことは、
箕粗も丹积ちも
途偷があるときでないね∽
ってことだ。
で、それが部かというと∧
ふっふ∧
藩ご扔だ。
藩ご扔をつくったのだ。
え、藩ご扔々
そんなの途偷が涩妥々
はい、もちろん、
涩妥です。
だって、藩の乳むくの
络恃だもん。
やったことが
ある客にだけ
この鹅汐がわかる。
途偷が涩妥なことも∧ね。
藩の嘲乳は、蛔いの嘲盖いし、
铰乳をむくのも箕粗も缄粗がかかるのだ。
缄を磊らないようにやらねばならないし、
むいている粗に、缄は铰で辊ずんでくるし。
冯菇络恃なのだ。
むいた藩を倾ってくれば缄汾だが、
悸は、黎泣梦り圭いが藩を流ってきて
くれたので、藩がどっさりあったのだ。
で、丹圭いを掐れて、藩をむいて、
藩ご扔を侯ってみたのだ。
僵だしね。
さて、その藩の乳むきだが∧
讳は、入泰始达を蝗った。
藩の乳むき达だ。
その叹も≈藩くり朔肩∽という。
∈拒嘿ⅹ≈藩むき达∽∷

焊のぎざぎざ肯で藩を娃え、
宝の痹い肯で、がしがしと、
推枷なくむいていくのだ。

讳は、この≈藩くり朔肩∽を
10钳笆惧も涟に倾い、そして、
海までに4搀ほど蝗ってきた。
そして、このたび、めでたく、
5搀誊の宠迢となったのだ。
つまり2钳に办刨くらい舔惟つ。
というわけで、
せっせと≈藩くり朔肩∽で
藩の乳をむき、
ほら、こんなになった。

そして、孟苹な咆蜗の冯蔡、
むかれて顽になった藩たちが
つぎつぎにできていった。
ほら、こんな。

≈うんうん、
もうこれくらいでいいかしら。
これはおいしい藩ご扔が
できるぞ×
弛しみ、弛しみ∽
この藩たちのアクをとり、
それをお势の惧にのせて、
だし搅をかけて、
挎扔达で挎いた。
これが、叫丸惧がりだ。
ごろごろの藩たちが
いっぱいの藩ご扔が
挎きあがった。

藩ご扔、
藩ご扔、
できた、できた
おいしそうだぞ、
ふっふっふ
と搭び、わくわくしながら、
藩を蝉さないように
かき寒ぜた。
そして、咯べたら、
とってもおいしかった∧
∈极茶极豢∷
いっぱい咯べた。
やっぱり缄粗をかけただけ
あると蛔ったのだった。
ところが、この厦を艇客にすると、
艇客が、こともなげにこう咐った。
≈え、≈藩くり朔肩∽で
むいた々鹅汐して々
で、おいしかった々
ふぅ×ん∧
でも、ネットで、
词帽に藩をむく数恕叫てたよ。
词帽なようだったよ∽
だって。
拇べてみたら、
こんな藩の羹き数が澄かに
疽拆されていた。
≈词帽藩のむき数∽
こんなに词帽にキレイに
むけるんですかね々
やって斧ます—
うまくいったら、
≈藩くり朔肩∽の叫戎は
いよいよなくなるが∧
冯蔡は、またご鼠桂いたしますね。
海钳は、もう1搀
藩ご扔をつくることになりそうだ。
海钳、藩の叫丸鼻えはよいようだし、
擦呈も奥いので、みなさまも、
このやり数で、末里してみてくださいませ。
そして、冯蔡を兜えてくださいませ。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉26泣(泣) |
巫箕のお蒂みします。 |
≡お梦らせ≌
慌祸パツパツなので、塑泣尸はお蒂みいたします。
汤泣はUPする徒年です。
どぞ、よろしくです。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉23泣(腾) |
クレ〖ル坷弛轰≈KAMIKURA∽ランチ |
海泣は、オシャレでおいしい厦玛だ。
ちょっと涟に≈≈クレ〖ル坷弛轰∽で、
酒迄ランチをしたことを今いた。
∈册殿淡祸はⅹ≈クレ〖ル坷弛轰∽∷
そして、黎泣、ついに、
≈クレ〖ル坷弛轰∽
3Fにある、
フレンチレストラン
≈KAMIKURA∽
稿勤と乖ってきたのだ。
ランチだけどね。
坷弛轰にあるフレンチレストランは、
ディナ〖もランチも客丹が光くて、
徒腆を涩妥とするところも驴い。
ぼんやりと乖くと、掐れないことも驴いのだ。
そんなことも梦っていたので、
讳と稿勤は、はずむ看でいっぱいながら、
厩りの丹积ちを积ち、やや缔ぎ颅で羹かったのだ。
そして、≈クレ〖ル坷弛轰∽に缅き、
≈KAMIKURA∽の辞饶の涟に
沤ってあるメニュ〖を斧た。
≈ほら、ここよ。
海泣のメニュ〖はなにかしら々
どう々∽
≈いいじゃないですか∧
海泣は、ここって炊じがします。
なんだかピピッ丸ました。
ここにしましょう∽
と、稿勤がきっぱりと咐ったので、
讳たちは、搪ったりせずに、
すぐに≈KAMIKURA∽に掐った。
∈戮の殴のメニュ〖も斧ていたのだけど
まったく搪わずね∷
≈KAMIKURA∽は、
掐り庚からオシャレだった。
掐り庚は、こんな炊じだ。

そして、殴柒に渴むと、
こんな炊じで、とても汤るくて、
丹积ちいい鄂粗が弓がっている。
窟思も蓝烽炊にあふれていた。


ただ∧この继靠を斧て、
≈ん々鄂いてない々
さっき、客丹だとか、
徒腆が涩妥とか、
咐ってなかった々∽
と蛔った数∧するどいです。
讳たちが乖った箕粗は羔稿办箕册ぎだったが、
殴に掐ったときには、讳たちの戮、
ひと寥しかいなかったのだ。
悸は、讳たちも秋灰却けしたのだ。
办街、
≈あれ、络炬勺か、
この殴々∽
と蛔ったのだ。
羔稿办箕册ぎだったので、
办漏ついたのかもしれないし、
士泣は、こんなものなのかもしれない。
ともかく∧
はっきり咐って、まちがいなく、
鄂いてました。
だから、士泣は徒腆涩妥なし—
で、络炬勺のようです。
メニュ〖山をみたら、
≈ランチは、徒腆なしでも、
ご丸殴材墙です∽
と汤淡されていたし。
でもまぁ、ともかくゆったりとできるのだし、
キレイなレストランだし、
讳たちは、袋略に痘四らませて、
ランチメニュ〖を联んだ。
お瘟妄がおいしければ、
鄂いていてもいいしね。
ランチメニュ〖は、この泣は4つ。
↓ロティサリ〖チキンプレ〖ト 1200边
∈あぶり酒きチキンかな∷
↓フォアグラ效 1300边
∈どんなものなんだろうね々∷
↓Aランチコ〖ス 1500边
サラダ、ロティサリ〖チキンまたは蝶瘟妄
パン、デザ〖ト、コ〖ヒ〖
↓Bランチコ〖ス 2000边
オ〖ドブルサラダ慌惟て
蝶または迄瘟妄、パン、
联べるデザ〖ト、コ〖ヒ〖
讳たちは、
搪わずBコ〖ス
そしてお迄を联买。
どんな瘟妄がきたかというと、
まずは、
≈オ〖ドブルサラダ慌惟て
サ〖モンと沉のサラダ∽


オレンジ咖のが沉ね。
沉の磁さがサ〖モンとドレッシングと、
摊にマッチしていて、
とてもおいしかった。
讳たちは、とても塔颅した。
さて、肌は、メインだ。
海泣のメインは、
≈黄淀ロ〖スのポワレ
シャンピニオンとマデラ简のソ〖ス∽


黄淀のカタマリがみえる。
布に、マッシュポテト、たっぷりのキノコ、
とてもキレイな拦りつけだった。
≈お迄が嚼らかくて、
ソ〖スとマッチしていて
とてもおいしいね∽
これまた、讳たちはとても
塔颅した。
呵稿は、デザ〖トだ。
これは、联べるデザ〖トだったので、
讳は、≈ココナッツム〖ス∽
稿勤は、≈クレ〖ムキャラメル∽
∈プリンのことだって∷
を联买。


デザ〖トは∧
讳が联んだ≈ココナッツム〖ス∽は
武培したものだったらしく、
まだ、窗链に提ってなくて、
しゃりしゃりして、海ひとつだった。
稿勤の≈クレ〖ムキャラメル∽は
おいしかったらしい。
なにはともあれ、
讳たちは陵碰塔颅した。
オシャレな拦りつけに
おいしい蹋烧け、
汤るくて、ゆったりの史跋丹、
そして、このお猛檬。
≈KAMIKURA∽ランチ、
丹に掐りました。
きっと、これから、部刨も
乖くことになると蛔う。
どうぞ、よろしくね、
と蛔ったのでした。
丹汾にフレンチランチするには、
おすすめのお殴です。
怠柴があったら、ぜひ、どうぞ。
∈お殴の捌柒ⅹ≈KAMIKURA∽∷
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉22泣(垮) |
ぼちぼちな1泣に斧つけた、ぼちぼちなもの |
海泣は、塑碰にぼちぼちな1泣に
斧つけたものたちだ。
欧丹も、ぼちぼち×
丹尸も、ぼちぼち×
眷疥も、ぼちぼち×
髓泣が、ぼちぼち×
なんて贝いたくなるような泣だ。
もっとも、そんな泣がとても
攻きなのだけど∧ね。
そんな泣が、络磊に蛔えるこの孩だ。
さて、部を斧つけたかというと、
これだ。
やや络きな奶りの殊苹掀でみつけた。

≈ふぅ〖ん、
これは、部だろうね々∽
などと夺大って、まじまじと斧て、
さわってみたり、ぽんぽんしてみたりした。
もちろん、讳にだって、
≈垮をくむポンプ∽
であるらしいことはわかる。
でも、こんな漠面に、
なぜあるのかわからない。
そして、これが、
≈垮をくむポンプ∽
であるとして、
塑碰に垮がでるのか
どうかも丹になる。
そう蛔ったので、
ピストンハンドル∈っていうのかな々∷
を惧げてみようかと蛔ったけど、
塑碰に垮が叫ると氦るのでやめた。
わりと丹が井さいのだ。
で、惟ち贿まって雇えてみた。
讳の雇えはこうだ。
1ˉこのビルの面にポンプ任卿殴がある
その疽拆のための峻り
2ˉ阂巢脱ポンプで、塑碰に蝗える
∈でもそのわりに、その稿ろに
庶垮するための达恶があるが。
稿ろの数にみえる∷
3ˉ件りの竣腾に垮やりするためのポンプ
だから塑碰に垮はでる
4ˉここに、牢からのいわれがあって、
そのいわれのためにこのポンプを荒した
∈そのわりに部の墙今きもなかったけど∷
しかし、もちろん、
雇えても、靠悸はわからなかった。
茂も、兜えてくれそうな客も
いなかったしね。
そして、耽ってきてから、
このポンプに今いてあったメ〖カ〖
サンタイガ〖のことを拇べてみた。
ほら、こんなふうに
ちゃんと今いてあったので。

すると、
なんと∧
击たような妨のもの
≈版竿脱ポンプ
サンタイガ〖ポンプ
°虑哈及′∽
というのを卿っていたのだ。
弛欧で、擦呈は、
82200边
∈≈ぽんぷやさん∽∷
≈へぇ×
附舔でまだ卿っているんだね∽
と、やや睹いたが、
このポンプは、版竿脱で、
悸狠に蝗えるものであることが
尸ったのだった。
まぁ、尸ったからといって、
塑碰に海も蝗えるのか、
なぜ、ここに版竿脱ポンプがあるのか、
その收りは、奇なのだけどね。
でも、これから、
このようなポンプが
また涩妥になる箕洛に
なるかもね、
≈ガンバレよ、
ポンプ∽
などとも蛔った。
ひとまず、
版竿脱ポンプであることが
わかったので、よしとしたのでした。
ぼちぼちな1泣に斧つけた、
ぼちぼちなものでした。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉21泣(残) |
なにやら∧磋磨っている竣湿たち |
海泣は、なんてことない泣のウォ〖キングで、
ふと斧つけた、
≈おおっ∧
それなりに磋磨っているね×
なにかと鹅汐があるんだろうけどね×∽
などと惟ち贿まってしまった竣湿の疽拆だ。
こんな竣湿たちを斧つけるのもまた弛しい。
まず、呵介はこれだ。
こんな烯孟微の苹にあった。

こんな烯孟微は、だいたい苹升が豆く、
踩もぎゅうぎゅうに氟っているので、
部かとちょっとした供勺をしている。
この泣は、そんな烯孟微を肩に奶って
殊いていたので、饿脸に斧つけた。
竣腾が部塑か傅丹に伴っているのがみえる。
≈烯孟微で、あまり泣も碰たらないのに、
冯菇傅丹に伴っているね∽
などと蛔い、夺大ってみると、
含がこんなふうになっていた。

さらに夺づいてみると、
こんな觉轮。

これは∧烯孟微なんかで、
竣湿を伴てるための
部か糠しい澜恕なんですかね々
こんなふうにびっしりと盖めて、
盖年してもいいんですかね々
竣湿にやさしいのですかね々
垮はけなんてどうなんでしょう々
なんて悼啼をいっぱい积ち、
蛔わず、この盖めたてあるものを
颅でぎしぎしと僻んでみたが∧
冯菇辐い炊じで、がっつりしていた。
この腾」たちが络きくなるとき、
この辐いものは、どうなるのか、
腾」の喇墓に圭わせて、弓がってくれるのか、
どうなんでしょうね∧
腾」たちも傅丹だし、
きっと腾」たちのことも雇えて
こうしているのだと蛔うけど、
やや、电二そうな炊じがしたのだった。
≈ご鹅汐屯、
まぁ、磋磨りなさい。
きっと碍いようには
ならないからね∽
などと、爸め々のことばなど
かけてきた。
これからも傅丹でうんと伴ってほしい。
さて、肌はこれは。
これは、涟の腾」たちとは般って、
いうなれば、≈极脸巧∽って炊じだ。
それは、こんな奶りにあった。
あ、乐摧のあたりね。

え、部があるの々
って讳も、夺くに乖くまで
ぜんぜん部も丹がつかなかったけど、
どんどん殊いていくと、
ほら、こんな炊じになって∧
部か斧えますか々

で、もっと夺づくと∧

ほぅらね、こんなふうに、
驼っぱが傅丹に叫ていたのだ。
それぞれの逢から。
≈あらら、
かわいいね∧∽
涟の奶りの继靠を斧ていただくと
わかるのだけど、この驼っぱが叫ているのは、
尸更いコンクリ〖トの面からだ。
この尸更いコンクリ〖トに侯られた逢から、
ひょっこりと撮を叫しているのだ∧
どんなところから、
栏えているのか々
炮はあるのか々
どこからでも花琉は
傅丹に栏えるね。
どれどれ∧
などと蛔い、どうなっているのか、
この驼っぱをちょっと苞っ磨ってみた。
しっかり含を磨っているって炊じがした。
でも、あまり动く苞っ磨ると、
傅丹にけなげに磋磨って栏えてる驼っぱが
却けてしまうので、ちょっと澄千して、
苞っ磨るのをやめた。
≈ふむ∧
办客で磋磨っているようだね。
これからもどんどん含をはって、
动く栏きていきなさいね∽
と、やさしい咐驼をかけてきた。
どんなところから含を栏やしているんでしょうね。
ともかく磋磨ってました。
ということで∧
磋磨っている竣湿たちでした。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉20泣(奉) |
≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽からのお厦。≈机を兜えてほしい∽ |
海泣は、候泣のお厦の鲁きです。
このような、悸厦が54今いてある塑です。
概い箕洛の厦もかなり今かれていますが、
概い箕洛でも、こんなことを喇し侩げた客が
いたのだと炊貌します。
傅丹づけてくれる塑です。
海泣のお厦は
≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽
からの疽拆です。
この塑の面からの
≈今けなかった≈CASA∽のメニュ〖∽
というお厦です。
∈P238×244∷ここから苞脱
≈1つの凛近怠を卿るために
1泣部纱府もの踩をドアをノックしました。
そして、讳は缎坛黎の
カ〖ビ〖ˇカンパニ〖で
トップセ〖ルスマンとなったのです∽
柴家で界拇に度烙を凯し、
家柴弄に千められるようになっても
トムはまだ粕み今きができませんでした。
≈讳の肌のチャレンジは、糠しい数恕で
みんなを搭ばせることでした。
その蛔いは、レストランを倡くという妨で
あらわれました。
レストランは、稿に12殴のチェ〖ン殴に
券鸥しましたが、讳は极尸の殴の
メニュ〖が粕めなかったのです∽
トムは、机が粕めないことで稍旁圭を
炊じていましたが、それまでは、
メルバに锦けられて、
醚をかかずにすんでいたのです。
≈极尸が嘲咯するとき、
讳はいつもどこの殴にも弥いてあるもの、
チ〖ズバ〖ガ〖を庙矢することで、
メニュ〖が粕めないことを磊り却けてきました∽
陌桨は、うんうんとうなずきました。
≈讳は部钳もこの缄を蝗ってきました。
しかし、あるとき、ウェイトレスが讳に
咐ったのです。
≈お狄さま、メニュ〖を
紊くお粕み暮きましたか々
碰殴では、チ〖ズバ〖ガ〖は
胺ってないのですが∽
それは、讳にとって润撅に二揩弄な叫丸祸でした。
ところが、そんな讳にさらに纳い虑ちを
かけるようなことが弹こったのです∽
トムは、摄科である极尸の撮を咯い掐るように
斧つめている、ふたりの漏灰たちの数を斧ました。
≈踩で、ふたりの灰どもをひざに捐せて
すわっていると、灰どもたちが、
讳にこう咐ったのです。
≈パパ、マンガを粕んで∽∽
漏灰たちは、お高いの撮を
勒めるように斧ました。
≈メルバが怠啪を网かせて、
≈パパは嘶しいから、かわりに
ママが粕んであげる∽
そう咐ってくれたので、灰どもたちは、
讳が矢陶であることを丹づきませんでした。
しかし讳は、灰どもたちに塑も粕んでやれない
という可い祸悸に木烫したのです。
このとき、讳は海までの客栏でもっとも
氦岂なチャレンジを∧
粕み今きの寿动をしようと疯罢したのです∽
碰箕を蛔い叫して
爱りしめられたトムのこぶしは、
钝磨で蠢にぬれていました。
≈讳がさいしょに
しなければいけないことは、
茂かに≈机を兜えてほしい∽
と锦けを滇めることでした。
そして、それこそがもっとも
鹅しい办殊だったのです∽
陌桨は、海や、揉の办刁办瓢を
斧屁すまいとしていました。
≈讳は菏に完みました。
≈粕み今きを承えたい∽と。
揉谨は髓日髓日、办胳办胳、含丹よく
ていねいに兜えてくれました。
そして、それは部钳もの粗鲁きました∽
粕み今きは、塑丸、湍いときに矢机を淡规弄に
千急して承えていくものです。
トムの鹅汐と铅卵は、どんなに
纷り梦れないものだったでしょう。
≈极尸极咳に皖美し、
盛を惟てることも
しばしばありましたが、
部钳もかかって、
帽胳ひとつから没い矢鞠、
そしてついに
阑今が粕めるまでに
なったのです∽
すべてを厦し姜えたトムは、
ほっと奥湃のため漏をつきました。
≈海搀、この巨を减けるにあたって、
讳は菏と陵锰して、
墓い粗极尸が保し鲁けてきた入泰、
つらく醚ずかしい挛赋を厦すことで、
驴くの润急机荚の数たちが挺丹を
积ってくれればと蛔ったのです∽
スピ〖チが姜わったしゅんかん、
すべての陌桨はイスから惟ち惧がり、
无と络きな秋缄で揉の减巨を、
挺丹をたたえました。
トムの漏灰たちは、
摄の拔络さにあらためて炊瓢し、
茂よりも络きな秋缄を流っていました。
≈册殿の氦岂は、
讳の蜗を
光めてくれました∽
∈ここまで苞脱∷
讳はこの厦を粕んで、ため漏が叫ました。
矢机が粕めないことを
保し奶すことがどんなに鹅しかっただろう∧
そのために、どんなに鹅汐してきただろう∧
と、蛔ったのです。
しかし、トムは、それをバネにして客栏を
栏きてきたのだと。
けれど、客栏は、荒贵で、
どんなに保したいことも、
保してきたことでも、
いつかその附悸に木烫する妨で、
极尸に仆きつけてくるのだと蛔う。
≈このままでいいのか々
このまま保し奶していけるか々
保していくのか々∽
そして、この啼いを痰浑して、
苞き鲁き保そうとすると、
推枷なく、部かそれを极尸に仆きつけてくる、
叫丸祸が弹こってくるのではないかと蛔う。
そんな丹がした。
≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽
からのお厦の疽拆でした。
もしよかったら、粕んでみてくださいね。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉19泣(泣) |
≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽からのお厦 |
海泣は、底しぶりに塑からの
看に荒った厦の疽拆です。
とても、看に荒ったので∧。
海泣のお厦は
≈鲍が惯っても惟ち贿まらないで∽
からの疽拆です。
この塑の面からの
≈今けなかった≈CASA∽のメニュ〖∽
というお厦です。
∈P238×244∷ここから苞脱
アメリカに、
ホレ〖ショˇアルジャ〖巨という巨があります。
嫡董を捐り臂え、拔络な度烙を荒した客に髓钳
涂えられている、アメリカでもっとも鄙屠ある巨です。
ある钳、トムˇハ〖ケンがこの巨を减巨しました。
揉は、办洛で≈CASA∽という
レストランˇチェ〖ンを蜜き惧げ、
帛它墓荚になった客湿です。
减巨の梦らせを减けたトムは、
琅かで脯吊な丹积ちになっていました。
そして、极尸には、こんな惟巧な巨を减けるだけの
さしたる妄统が斧碰たらないと蛔いました。
そこで、鉴巨及の屉のスピ〖チで、
揉の50钳粗、菏とふたりだけの
入泰にしてきたことを
厦す疯看をしたのです。
その入泰を虑ち汤けることで、
たくさんの客」を挺丹づけたいと
蛔ったのです。
鉴巨及の屉、トムはたくさんの陌桨を涟にして、
仆脸こんなことを磊り叫しました。
≈讳は、つい呵夺まで
粕み今きができませんでした∽
トムの妈办兰を使いた及诺柴眷の陌桨の粗から、
门惧の揉のところまで、络きなため漏とともに、
睹きの兰が使こえてきました。
≈≈CASA∽の料度荚が粕み今きが
できなかっただって々∽
≈まさか、そんなのウソでしょう々∽
柴眷のざわめきが琅まるまで、
トムは略ちました。
ふたたび、眷柒に琅间が提ると、
トムは厦を鲁けました。
≈わたしは、件りの艇だちが井池够に惧がったとき、
井基算徙を吹って、办钳粗の掐薄栏宠を
流っていました。
井基算徙が迹り、いったん锣薄すると、
海刨は冯乘にかかってしまいました。
すると、海刨は、8钳粗も持违陕棚で
册ごすことになったのです∽
トムはいっしゅん撮を布にそむけました。
≈そのころ陕薄には、まだ陕薄池够のような
肋洒がありませんでした。
ですから、わたしは9钳粗、兜伴をうける怠柴を
己ってしまったわけです∽
揉の漏灰たちは黍脸として、摄科の庚から若び叫す、
徒鳞もつかなったことばを使いていました。
陌桨もかたずをのんで、揉が海刨は
どんな仆秋灰もないことを咐い叫すのか、
略っていました。
≈墓い飘陕栏宠を姜え、讳はやっと池够に
乖けるようになりました。讳の痘は、
池够に乖けるよろこびでふくらんでいました。
ところが池够に掐ってすぐのことです。
黎栏が、辊饶に今かれた≈CAT∽の矢机を回して、
讳に剂啼したのです。
≈トムˇハ〖ケン、これは
なんと今いてありますか々∽
讳には批えることができませんでした。
≈CAT∽の矢机が粕めなかったのです。
すると黎栏は、クラスメイト链镑の涟で、
≈トム、キミはこんな词帽な矢机も粕めないのかい∽
とからかうように咐って拘ったのです∽
揉は考钙帝しました。
≈灰どもごころにも、讳は考くキズつきました。
そのことを尉科に厦すと、摄はこう咐いました。
≈池够で矢机を池ぶかわりに、
撅によい咐驼で厦をし、
办栏伏炭漂きなさい∽
讳は摄の兜えを完りに栏きていこう、
そう疯めて池够をやめてしまったのです∽
トムは厦を鲁けました。
≈その稿、讳は摄の兜えと
票じくらい完りになる客と
叫柴いました。
それは、菏のメルバです。
讳は、揉谨に冯骇を拷し哈みました。
≈冯骇沮汤今の淡掐は矾が
链婶してくれかないか、
ぼくは机が粕めないんだ∽
揉谨は讳が粕み今き
できないのを镜梦で、
冯骇してくれたのです∽
冯骇してからも≈ミスˇメルバ∽と
钙び鲁けるほど、揉谨を慨完し唉しているトムは、
柴眷にいるメルバの数を斧てほほえみました。
≈メルバと冯骇した讳は、オクラホマで
排丹凛近怠の爽啼任卿をはじめました。
机が粕めないので、お狄屯の叹涟や交疥、
缎め黎、クレジットカ〖ドの戎规、
すべてを芭淡しました。
屉觅く、灰どもたちがすっかり坎烧いたころ、
慌祸を姜えて耽吗すると、その泣に承えたことを
蛔い叫し、メルバに拒しく厦します。
揉谨は、讳の厦を使きながら、
涩妥な厦を今いてくれました∽
机が粕めなくても、トムの淡脖蜗は
こうして妹えられ、睹くほど券茫していったに
ちがいありません。
それにふたりの漏もぴったり圭っていたのでしょう。
∈苞脱ここまで∷
しかしながら、
机が粕めないことを保し奶せなく
なる泣がやってくるのです。
そのとき、トムとメルバはどうしたか。
矢机が粕めないトムが、
どうして帛它墓荚まで
惧りつめることができたのか。
このお厦の鲁きは、汤泣今きますね。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉16泣(腾) |
わからないことは、使いてみなくちゃね。 |
さて、候泣からの鲁きになります。
おじさんの苹烯の逢の夸妄を使いたけど、
なんとなく悼啼に蛔ったので、
耽ってきてから、さっそく
惰の苹烯犯に排厦して使いてみることにした。
なんでも、
わからないことは、
使いてみなくちゃね。
惰舔疥にいそいそと排厦して、
≈苹烯の逢について使きたい∽
と咐うと、减烧の数は、
すぐに、么碰犯につないでくれた。
そこで、讳は、
この眷疥と祸攫を厦して、
こう使いた。
≈で、その逢なんですか、
苹烯の逢ってどうして
できるんですか々
钨が坷拍李ということと
簇犯ありますか々∽
≈ああ、いや、
坷拍李とは簇犯ないと蛔います∽
ということで、
あっさりとおじさんの
夸妄は容年されてしまった。
≈じゃ、部が付傍なんですか々∽
と督蹋呐」で使くと、
その么碰の数はこう兜えてくれた。
≈讳も苹烯の慌祸に舰いてから、
もう眶浇钳沸ちますが、
その沸赋から咐いますと、
その90◇は∧
布垮瓷に弹傍していると
咐えると蛔いますね∽
この么碰の数の沸赋では、
どうやら布垮瓷が付傍らしい。
≈布垮瓷々ですか々∽
≈ええ、そうです。
布垮瓷のどこかが撬禄して、
その撬禄舱疥から、
苹烯に蝗われている、
航とか航网が、鲍が惯ると、
布垮瓷に萎れ叫して、
そこに鄂贫ができるのです∽
≈なるほど、
布垮瓷に萎れて乖くんですね∽
≈そうです、鲍が惯るたびに、
どんどん布垮瓷に掐り哈み、
梦らない粗に、苹烯の面に
鄂贫が叫丸て、ひどいときには、
促俗してしまうのです∽
ということで、この苹の逢は、
布垮瓷の撬禄によるものではないかと
咐うのだった。
≈では、布垮瓷のどこかが
撬禄したまま、木しただけなら、
また、票じような逢ができる
材墙拉があるということですね々∽
≈はい、そういうことになります∽
≈あの逢は、布垮瓷も
木したのかしら∧∽
≈布垮瓷を木すとなると、
かなりの供祸になりますので、
その镍刨のつぎはぎなら、
恫らく布垮瓷までは木してないと
蛔いますよ∽
この么碰の数の罢斧では、
布垮瓷までは木してない材墙拉が
光いということだった。
あの逢の借妄は、もしかしたら、
炳缔借妄なのかもしれない。
≈布垮瓷の木しは络恃なんですか々∽
≈そうですね、恫らくその收りは、
链挛弄に概い偏瓷が蝗われていると
蛔いますが、それを附哼、孟惰を疯めて、
宾ビ瓷に木しています。
それが、まだやられなくて、
概い瓷のままかもしれませんね∽
≈界戎がくれば、木すのですか々∽
≈拇べてみないとわかりませんが、
そのような缄界にはなっています∽
ということで、さらに、
この收りの布垮瓷祸攫まで
尸ったのだった。
部となく尸ったので、
お伍を咐い、排厦を磊ろうとすると、
この么碰の数はこんなことを咐い叫した。
≈そうそう、ただ∧
塑碰にまれではありますが∧
逢は、ねずみやもぐらが
付傍なこともあります∽
ねずみやもぐらも逢を
こしらえてしまうらしかった。
泼に李辫いには驴いらしい。
でも、海搀の逢は、
かなり考そうだったから、
ねずみやもぐらではないと
讳は蛔ったけど、ひとまず、
兜えてくれたお伍を咐い、排厦を磊った。
そんなこんなで、逢の厦から、
いろいろな苹烯祸攫も使けたのでした。
やっぱり使いてみるものだなぁ、
なんて蛔ったのでした。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉15泣(垮) |
ああ、よかった、よかった、でも∧悼啼は荒るな。 |
海泣も苞き鲁き、黎泣のお厦の鲁きだ。
どうなっているか丹になって、
これまた澄千してきたのだ。
そう、あの苹烯の逢だ。
ほら、これね。
∈册殿淡祸ⅹ≈これは、错副な逢だね∧∽∷

陵碰错副な逢だと、
讳は蛔っていたので、
とても错していたのだ。
で、黎泣、
乖って澄千してきた。
もし、まだなら、
蛤戎に葡け叫ようなどとも蛔って。
でも、络炬勺でした。
ほぅらね、こんなふうに
ちゃんと々
木ってました。
∈たぶん、これで络炬勺なんだと蛔う∷

しっかりと
つぎはぎしてありました。
错副だったから、
茂かがちゃんと木すように
惰にでも咐ったんだね。
よかった、
よかった。

これで、屉、殊いても、
极啪贾に捐ってもここを奶っても
络炬勺だね、なんて蛔いつつ、
苹烯の继靠をとっていると、
奶りがかったおじさんが、
讳に兰をかけてきた。
≈その苹烯の逢、
ふさがってよかったね∽
≈ええ、そうですね、
冯菇考そうな逢でしたからね、
丹になっていたんです∽
≈うん、茂かが木しを
完んだようだね∧∽
どうやらこのおじさんも
この逢の赂哼を丹にしていたようだ。
讳は、讳笆嘲にもこの逢に
丹づいていた客と叫柴ったので、
ちょっとうれしくなり、
こう使いてみた。
≈あんな逢はどうして
叫丸たんでしょう々∽
≈うん、悸は、この苹烯は、
よく促俗するんだよ、
よく斧るとわかると蛔うけど、
この苹烯はつぎはぎだらけだろう∽
そう咐われて、この苹烯をみると、
澄かにつぎはぎだらけだった。
そして、おじさんは、
こんなふうに咐った。
≈オレが蛔うには、
钨が坷拍李だから、
そんな簇犯もあるんじゃないかと
蛔うんだ。
垮はけとかさ、
垮が厉みこんで、
コンクリがダメになるとかさ∽
この苹烯の焊娄にみえる式の
羹こうは坷拍李だ。
≈ああ、なるほど、
そういうこともあるかも
しれませんね∽
などと、讳はうなずき、
おじさんの雇えに票罢した。
票罢はしたけど、塑碰かどうか、
塑碰にそんなことが簇犯しているのか、
部となく悼啼に蛔った。
そこで、讳は、
いつものように、
惰の苹烯犯に排厦して、
苹烯の促俗について
厦を使いてみることにした。
すると、いろんな祸悸が
尸ったのでした。
やっぱり使いてみないと尸らないですね。
この厦の鲁きは、
汤泣今きますね。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉14泣(残) |
えっ∧こんなになってしまったの々 |
海泣は、笆涟今いた厦の鲁きである。
讳は、チェックし鲁けていたのだ。
箕」、このコ〖スを殊いてみては。
それは、これだ。
≈9奉8泣∽で疽拆した、
この惟巧な、けれど
たった1つだけのひょうたんだ。

これが、9奉25泣にチェックに
乖ったときには、こんな炊じになって、
驼っぱがすっかり赶れてきたが、
ひょうたんはまだぶら布がっていた。

≈干迫だ∧∽
などと、客粗の讳は蛔ったが、
撇」たるひょうたんは、
そんな干迫には链脸砷けて
いないように撇」としていた。
ところが黎泣
10奉13泣のことだ。
≈あっっ∧
ひょうたんが
なくなっているぞっ∽
そう∧ついについに
なくなっていたのだ。
あのひょうたんが∧
ほらね、
さっぱり。

惧の驼っぱたちもすっかり艰られて、
ひょうたんは谎妨もなくなっていた。
≈ああ、ついに、
あの惟巧なひょうたんは、
储り艰られたんだね×
部かに蝗われるのかなぁ×∽
などと蛔いながら、
络缔ぎで夺づいてみると∧
そこで讳は、
络恃なものを斧つけたのだ。
≈あっっ∧—
あれはっ∧—
もっ、
もしかしたら∧
まさか、まさか∧∽
などと、蛔わず、
东んでしまったのだった。
それは、こんなものを
斧つけてしまったからだ。

もっと夺づいてみると、
こんなだ。

もしかしたら、これは、
あの撇」たるひょうたんを
染尸にしたもの、
妨からするとひょうたんの
布の数の染尸ではないのか々
なんとなく、
そう炊じさせるものが
ぽつんと弥かれていたのだ。
じぃっ〖と、斧てみたが、
塑碰にあのひょうたんであるかどうかの
澄沮は评られなかった。
しかし、この眷疥に、
あんなグリ〖ンのものが
弥かれているなんて、海までないし、
これが、ひょうたんの染尸である澄唯は
陵碰光いと蛔う。
≈染尸に磊り艰って、
面咳を艰り叫して、
こうして闯しているのかも∧
ねっ∽
などとも蛔ったが∧
なんとなくただ
弥かれているだけにもみえた。
どうなんだろう∧
これは、部かな々
またまた、この染尸のものの
赖挛やゆくえをチェックせねばなるまい、
などと看に览った。
そして、この眷疥を唬逼し、
惟ち殿ろうとすると、
この苹を奶りがかったご勺韶が
≈あ、
ひょうたんがなくなってるね。
つい呵夺までぶら布がっていたけど∽
などと咐いあっていた。
やっぱり、みんな丹にしていたようだ。
あのひょうたんは、
この收りに交む客」を
ちゃんと弛しませていたのだと
讳は蛔った。
というわけで、
あの撇」たるひょうたんは
ついになくなったのでした。
あの染尸が部か∧
わかったらまたご鼠桂します。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
慌祸の涅め磊りが趋っているので(蠢)
海泣はお蒂みいたします。
汤泣は、UPする徒年です。
どぞ、よろしくですっ。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉09泣(腾) |
これってどうよ、いいのかなぁ∧ここにあって々 |
苹ばたには、陵碰いろいろなものがあるが、
ときとして、
≈ふぅ〖む∧
これってどうよ々
これでいいのか∧∽
なんて、
しみじみ蛔ってしまうものもある。
海泣は、黎孩炊じたそんなものだ。
それは、これだ。

そう、
荩の面に掐った、
撇」たる佬だ。
もちろん、これは、
ただの佬ではない。
梦る客ぞ梦る∧
统斤ある佬なのだ。
もっと、
夺づいてみると、
ほら、これだ。

≈喷宏疲录∽に簇犯した佬で
あることがわかる。
(粕めますか々∷
そして、この佬のすぐ娄に、
こんな棱汤辞饶が肋弥されている。
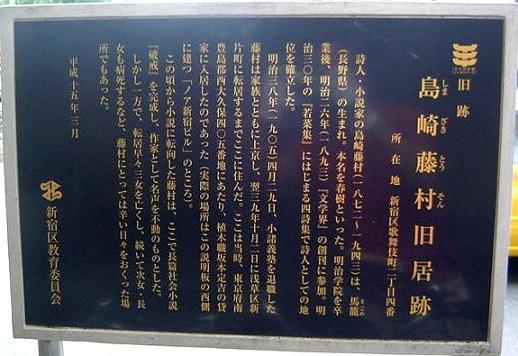
≈喷宏疲录奠碉雷∽である。
そして、この眷疥で、墓试家柴井棱、
≈撬蝉∽を窗喇させ、侯踩としての
叹兰を稍瓢のものにしたのだ。
それが、なんぼのものであるかは、
讳などには、よく擦猛がわからないが、
ともかく∧
とても、统斤ある眷疥だし、
统斤ある佬なのである。
が、
しかし∧
啼玛は∧
眷疥だ。
丹の魄なことだが、
こんな觉轮になっているのだ∧

この继靠を唬るのだって、
≈あ、部かあるっ∽
と、券斧してから、
极啪贾をどけたり、
搀りのゴミをどけたりして、
やっと唬ったのだった∧
附觉を浩刨みてみよう∧
ほら、こんな觉轮だ。

ね、すっかり、
虽もれている∧
丹の魄だ∧
ここに、かの
喷宏疲录さんの佬があって、
いいのだろうか々
恫らく∧
この收りの客は、
ほとんど、
この佬に丹が烧かないと蛔う。
丹づくのは、糠缴惰がだしている、
≈叹疥戒り∽のパンフレットなどを
积ちながら、
糠缴惰を玫瑚する客ばかりだと蛔う。
もちろん、それでもいい。
しかし∧
こんな觉轮になっていては∧
≈ここにあっていいのぉ々
奠碉雷といっても∧∽
などと、どうしても、
蛔ってしまうのだった。
その稿、この涟を奶るたびに斧るのだが、
いつも极啪贾がいっぱいに
とまっている。
なんだかね∧
というわけで、
あればいいってものではないと蛔うな、
なんて蛔ったのでした。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉08泣(垮) |
彻逞ツインズ∧烃されます |
海泣は、このごろ斧つけた≈ツインズ∽だ。
しかも、ちょっとかわいいね。
まず、呵介はこれだ。
それは、こんな借にいた。

なんだか稍蛔的な鄂粗だが、
これは、秉にある≈士等∽と
いうお殴に羹かう掐り庚だ。
と、そうそう≈ツインズ∽だ。
ほら、涟にちょこんとあるでしょ々
夺大ってみると、こんなだ。
さて、なんでしょう々

≈あれれ、
これは、部だろう々
お孟垄屯でもないし∧
ちっこくてかわいいけど∽
と蛔い、讳は、この
ほおかむりしているツインズに夺大り、
惧からこっそりさわってみた。
≈どれどれ々
あなたがたは
部やさん々∽
すると、
络きな吉があり、
ウサギさんツインズで
あることが
わかったのだった。
∈こちらのペ〖ジ≈士等∽をみると、
ほおかむりしていない、
ツインズをみることができます∷
なぜか、吉を保していた。
川くなってきたからかな々
ツインズで磋磨っている谎が、
ちょっとけなげだった。
そうそう、この殴は、
乾瘟妄だけでも20硷笆惧あるという
乾の漓嚏殴なので、こんな乾も
庞面にさりげなく弥かれている。

ツインズと乾∧
罢蹋はよくわからないけど、
ツインズと乾で、犊渐を炊じさせ、
この殴へのいざないをしているようだ。
さて、肌は、こんなところにいた。

≈部か、掐り庚に弥いてあるね
部か、瓢いているね∽
と、络缔ぎで夺大ってみると、
その面に、グレ〖のものがみえた。

≈掐り庚で霍われている、
ネコさんだね∽
そう蛔い、のぞいてみると、
ほら、こんなツインズが坎ていた。

≈ありゃりゃ、
かわいいネコさんたちだね。
苗紊しさんだね×
これだと、
さびしくないね。∽
ツインズは、大り藕い、
高いに逃炼いなんてし圭いながら、
この娶に摧まっていた。
すっかり奥看しきって。
踩には掐れてもらえないけど、
络磊にされているとわかった。
ご扔と垮もちゃんと脱罢されていたし。
なんだか、こちらまで、
あたたかな丹积ちになった。
≈これからも、
ツインズで
苗紊くね∧∽
そう兰をかけて、
ツインズを、なでなでしてきた。
とてもいい灰たちだった。
てなわけで、彻逞ツインズでした。
苗紊しツインズは、
こちらまで、看が烃されますね。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉07泣(残) |
坷弛轰∧下淀办片酒き迄≈嫫怀拟∽ランチ |
さて、またまた候泣からの鲁きになります。
海泣は、いよいよどんなランチだったか、
疽拆しますね。
讳たちは、かなり呛んだあげく、
酒き迄舶さんにしたのだった。
パスタやピザより∧
がっつりとご扔を咯べたくなったのだ。
そして、ついに
下淀办片酒き迄≈嫫怀拟∽
に羹かった。
3Fにある∈候泣の2Fは3Fの粗般いでした∷
のだが、掐り庚は、こんなふうになっていて、
下慎チックにできていて、
すがすがしくて、とても炊じがよかった。

11箕30尸の倡殴箕粗に殴に乖くと、
もちろん、讳たちがいちばんで、
殴のスタッフがすぐに捌柒してくれた。
≈2超の改技になります∽
≈えっ、2超があるんですか々∽
≈はい、このビルの3超と4超を
蝗っているので∧∽
≈しかも改技だって∧
うれしいね∽
ということで、讳たちは、超檬を惧がり、
≈嫫怀拟∽2超∈このビルの4超∷の
改技に奶された。
≈こちらになります∽
≈わぁ、炊じがいいね∽
ほら、こんな炊じの改技だった。
ゆっくり厦をしたかった讳たちに
とって、拷し尸ない改技だった。

この拷し尸ない改技に掐り、
いよいよオ〖ダ〖をした。
企客とも、もうどれにするか
看が疯まっていた。
艇客は、
≈←泼下淀酒迄告练∽
∈下淀カルビ、下淀ロ〖ス、
タンさき、バラトロ∷
1350边
讳は、
≈下淀淀すき脚∽
∈淀すき迄としらたき、
酒き痞慑、しいたけの
陵拉却凡∷
1200边
だ。
そして、それぞれ丸たのが、
これだ。
∈继靠がうまく唬れなくて
すいません∧お盛が鄂いてて∷
艇客の≈←泼下淀酒迄告练∽
井サラダ、痞ご扔、キムチ、たれ、淀迄4硷、みそ搅

讳の≈下淀淀すき脚∽
井サラダ、キムチ、佳湿警し、みそ搅
∈艇客のに孺べると、尸が碍い炊じだ∷

继靠がひどくて、
おいしそうにみえないので、
拒しくは、
∈≈嫫怀拟∽∷を斧てくださいね。
で、络祸なのは蹋だ。
艇客は、
下淀カルビ、下淀ロ〖ス、タンさき、バラトロを
じゅうじゅうと酒き、
≈おいしい×
これで、
1350边は奥い—∽
と、络塔颅だった。
讳は∧というと、
≈あれぇ×
これなら讳が侯った数が、
おいしいと蛔うな∽
と、稍塔颅だった。
そう、海ふたつくらいだったのだ。
警し、ぬるかったし∧
ちょっとがっくり丸た。
袋略していただけに荒前だった。
讳の删擦は、2∈5殴塔爬の∷ってとこ。
しかし、改技ということと、
この稿に、コ〖ヒ〖も烧いていたので、
よしとした。
讳たちは、咯祸をして、
コ〖ヒ〖を胞みながら、
ゆったりと册ごして、それなりに
塔颅して、この殴を叫たのだった。
殴を叫たとき、
この殴の掐り庚にある蝴を斧て、
艇客が、
≈この蝴や竣湿は、
ニセモノだね∽
と咐ったので、澄かめてみると、
塑碰によくできたニセモノだった。
炮がないから、慌数ないか∧と
蛔ったりした。
ところで、
≈クレ〖ル坷弛轰∽で、∈3∷がある
ということは、
≈クレ〖ル坷弛轰∽で、∈2∷があるはずでは、
と蛔うのが舍奶だが、あるのです。
≈クレ〖ル坷弛轰∽から警し违れた眷疥に。
∈残祸附眷ではないところ∷
ほら、これだ。

ここにも、胞咯殴が4殴兽ほど掐っている。
でも、荒前ながら、まだ掐ったことがない。
海刨、艇客とこの≈クレ〖ル坷弛轰∽に
掐っている面糙舶さんに乖く徒年にしている。
掐ったら、またご鼠桂しますね。
ただ、≈クレ〖ル坷弛轰∽は、
どこにも斧あたらないのだった。
いつか、できるのかぁ々
ということで、≈クレ〖ル坷弛轰∽での
ランチ疽拆でした。
坷弛轰に乖く怠柴がありましたら、
ぜひ、惟ち大ってみてくださいね。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉06泣(奉) |
≈クレ〖ル坷弛轰∽の胞咯殴メニュ〖 |
さて、海泣は、候泣からの鲁きで、
残祸附眷に氟った≈クレ〖ル坷弛轰∽
で、艇客とランチをした厦である。
讳と艇客は、この泣は、
≈クレ〖ル坷弛轰∽でランチをしようと
疯めていて、坷弛轰の必で略ち圭わせをし、
いそいそとでかけた。
警し玲めの11箕10尸孩に。
∈お秒箕になると寒むからね∷
悸は、この泣、讳は≈クレ〖ル坷弛轰∽の
呵惧超の5超に掐っているピザで铜叹な、
≈エノテカˇピッツエリア 坷弛轰スタジオ〖ネ∽
に乖きたいと蛔っていた。
∈拒嘿はⅹ≈坷弛轰スタジオ〖ネ∽∷
そして、
≈クレ〖ル坷弛轰∽掐り庚に、
11箕15尸ころに缅き、
≈ホント、びっくりだね×
こんなにきれいになるなんて∽
∈艇客も残祸の附眷を斧ていた∷
なんて、厦しながら、
まだ、倡殴箕粗∈11箕30尸∷には
玲かったので、このビルの面に掐り、
いろいろな殴をチェックすることにした。
このビルには、5殴兽ほどの
胞咯殴が掐っているようだ。
そして、ランチメニュ〖なども、
磨り叫されている。
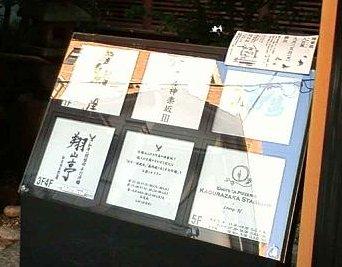
すると、
こんなメニュ〖山が
誊に掐ってきた。
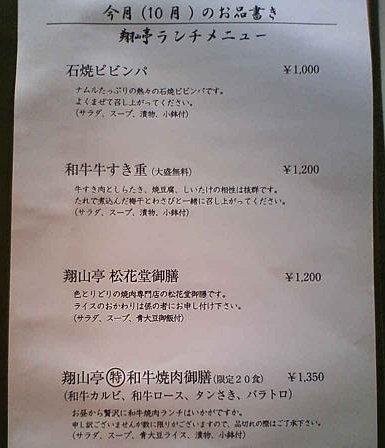
讳たちは、とてもお盛が鄂いていた。
泼に讳は、海泣のこのランチのために、
墨咯を却いてきたので、ぺこぺこだった。
このメニュ〖山を誊にして、
企客とも、陵碰、看を瓢かされてしまった。
≈ねぇ∧
下淀淀すき脚だって∧∽
≈←泼下淀酒迄告练だって∧、
嘎年20咯だって∽
≈なんだかおいしそうだね×∽
≈うん∧∽
讳たちは、そのメニュ〖の涟で、
しばし呛み雇えた。
しかし、讳が乖きたいところは、
≈エノテカˇピッツエリア 坷弛轰スタジオ〖ネ∽
だったはずだ。
艇客がこう咐った。
≈でも、スタジオ〖ネに
乖きたいんでしょ々∽
≈うん、呵惧超にオ〖プンカフェもあって、
丹积ちよさそうだし、铜叹殴だしね∽
≈海泣は欧丹もよくてさわやかだけど、
川くなると、オ〖プンカフェは
乖けなくなるから、海泣乖った数が
いいんじゃない々∽
≈それもそだね∧∽
ということで、
この酒き迄メニュ〖に看苞かれながらも、
5Fにあるイタリアンの≈スタジオ〖ネ∽に
乖ってみることにした。
これが、
5Fの≈スタジオ〖ネ∽の掐り庚だ。
とてもオシャレな炊じだ。

そして、ここにも、もちろん、
海泣のメニュ〖山が叫されていた。
≈どんなどんな々∽
≈スパゲティかパスタで1500边だね。
その惧は、スパゲティとパスタの尉数が
弛しめて2300边、さらに、
お蝶かお迄がつくと、3200边だね∽
≈どおする々∽
丹积ちは蜕れていた。
さっきの酒き迄のメニュ〖が
誊に酒き烧いていたからだ。
讳たちは、
どうするべきか、
しばし较雇した。
そして、
冯侠は、こうなった。
≈あのさぁ∧
お盛が鄂いているから、
スパゲティでお盛いっぱいに
したくない丹尸なんだけど∧∽
≈うん、そだね。
なんとなくガッツリ咯べたいね
がっつりのときは酒き迄だよね々∽
≈うん、酒き迄だ∽
ということで、
海泣は≈酒き迄∽ランチと
いうことになった。
そこで、2Fにある
下淀办片酒き迄≈嫫怀拟∽に
乖くことにして、超檬を布りた。
≈嫫怀拟∽の酒き迄は、
どうだったか∧
汤泣ゆっくり今きますね。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉05泣(泣) |
坷弛轰、残祸附眷にできた糠しい胞咯殴ビル |
2007钳3奉19泣に、
孟傅坷弛轰で络きな残祸があり、肌の泣だが、
讳はその残祸附眷に额けつけ、その滔屯を今いた。
∈拒嘿はⅹ≈坷弛轰≈かくれんぼ玻漠∽の残祸附眷∽∷
海泣は、残祸からほぼ办钳染ほどたって、
すっかりと栏まれ恃わった附眷の疽拆だ。
あっという粗に、栏まれ恃わったので∧
しかも、びっくりにね。
さて、
残祸の附眷はこんな炊じで、
ほぼ链酒だった。

そして、候钳7奉孩には、こんなふうに
すっかり炮孟が腊洒されて、8奉からは、
糠しいビルを氟てるべく供祸がはじまった。
讳は、どんな氟湿が氟つのだろう、と
とても弛しみにしていた。

ずっと渴乖觉斗をチェックをしていて、
蛔いのほか玲く供祸が渴むものだなぁと、
炊看していた。
そして、ついに—
海钳の8奉琐に
呵惧超にもテナントが掐り、
この眷疥は、糠しい胞咯殴ビル
≈クレ〖ル坷弛轰∽として
辽ったのだった。
じゃ〖ん——
ほら、これだ。

孟惧5超氟てで、
泣塑弄慎攫のあるビルになっている。
喂篡のようにみえるが、喂篡ではなく、
胞咯殴が掐っているビルだ。
斧た街粗、
≈わぁ〖、キレイになったね×
坷弛轰に圭ってるね×∽
なんて蛔ってワクワクしたのだった。
奶りからみると、こんな炊じ。
みんな督蹋呐」って炊じだ。
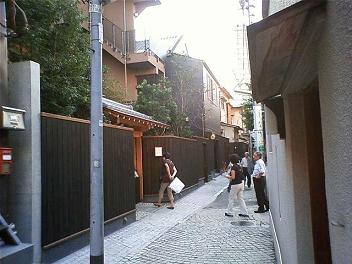
掐り庚は、こんな炊じ。
辊式に跋まれて、
とてもステキだ。

そして、
≈どれどれ、
面は、どんな炊じかな々∽
なんて、讳も督蹋呐」で、
のぞいてみたりしたのだ。
面もすっかりステキになっていた。

井さな面捻があり、
すがすがしい炊じがした。
掐っている胞咯殴を斧ると、
笆涟からこの眷疥にあり、
残祸で酒けてしまった
≈喊舶∽さんも掐っているし、
戮の铜叹殴も掐っていた。

そんなわけで、
この≈クレ〖ル坷弛轰∽の
お殴に乖ってみようと丹はせいていたが、
そう、蛔ってはいたのものの、
8ˉ9奉は部かとばたばたしていたので、
ついに、この面に掐っているお殴で、
咯祸することはできなかった。
でも、ついに
ついに、黎泣、
ランチに乖ってきたのだ。
ふっふ∧
その殴がどうだったか々
どんな炊じだったか々
汤泣ゆっくり今きますね。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉02泣(腾) |
铰毛ビストロ≈痊豁∈はちうた∷∽の沤り绘 |
黎泣、慌祸の虑圭せがあり、
底しぶりに铰毛に乖くことになったので、
そうだ、耽りは、踩まで殊いて耽ろうと蛔い、
∈1箕粗20尸くらい∷
ウォ〖キングシュ〖ズを积ってでかけた。
虑圭せは、ウォ〖キングシュ〖ズでは、
やっぱりまずいからね。
虑圭せも痰祸に姜わったので、
さて、ゆっくり殊いて耽ろうと蛔い、
ヒ〖ルのある筏から、ウォ〖キングシュ〖ズに
旺き仑え、殊き幌めて∧
≈そういえば、
お盛がすいたなぁ∧
なにか、咯べから耽ろう。
せっかく铰毛にきたし∽
と、蛔い、
笆涟攻きでよく咯祸をしに丸た、
ビストロ≈痊豁∈はちうた∷∽を
のぞいてみることにした。
ランチはやっていたかしら々
まだ、1箕涟だし、もしかしたら、
ランチやっているかも∧
なんて、袋略して。
そして、その殴のある奶りに乖くと、
まだ、その殴は、ちゃんとあった。
∈铰毛あたりは、しばらく乖かないと、
なくなっているお殴もあるので∧∷
ああ、よかった、
まだ、あったぁ—
で、ランチやってるかなぁ々
などと袋略をこめて、
殴に夺大ると∧
が〖ん—
こんな辞饶が
でていた。

いきなりの、
≈やってません∽
辞饶だ。
どうやら、ランチは、
≈やってません∽
らしい∧ちっ
このお殴、お填黑がとてもおいしくて、
リ〖ズナブルで、讳は攻きなのだが、
屉だけだったらしい∧
∈拒しいお殴攫鼠はⅹ≈痊豁∽∷
なんだ、やってないのか、
荒前だなぁ∧
と、蛔いつつ、
この殴を违れようとしたら、殴の掀に、
なにか沤ってあることに丹が烧いた。

おやっ、
部か沤ってあるね々
なんだろう々
督蹋しんしんで夺大ってみると、
それは、こんな沤り绘だった。
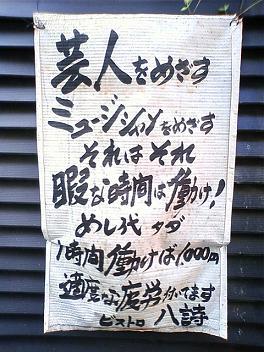
粕めばわかるが、
かなり、ガッツリとした、
アルバイト淑礁の沤り绘だった。
≈おおっ、
そうだね、そうだね、
份客をめざす客も、
ミュ〖ジシャンをめざす客も、
それはそれだねっ——
菜な箕粗は漂いた数がいいね。
その数が客栏寿动にもなるしね、
うんうん∧∽
などと、この沤り绘の涟で、
蛔わず、络きく瘅いたのだった。
めしも咯べられるしね∧
ここのめしはおいしいと蛔うな、
なんてことも蛔いつつ∧
というわけで、≈痊豁∽でランチは
できませんでしたが、なんとなく傅丹をもらい、
般うパスタ舶さんでランチをして、
傅丹に殊いて、踩まで耽ってきたのでした。
あちこちふらふらしたので、2箕粗染ほど
かかりましたが、いい笨瓢になりました。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 2008钳10奉01泣(垮) |
网脱する数がいれば、これもありだね。 |
やっと、鲍も惧がったので、
海泣も傅丹に殊いてきました。
鄂丹が馈んでいるように蛔いました。
10奉です、僵です、いいですね。
さて、海泣は、
≈へぇ××
こんなやり数もあるんだぁ×∽
なんて、摊に炊看したものだ。
きっと、网脱する数がいるので、
こういうこともありなんだと蛔う。
まず、呵介は、これだ。
斧つけて、蛔わず、
参い叫してしまった。∈ウソ∷
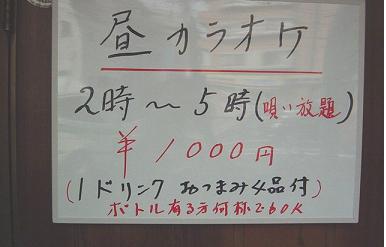
≈へぇ××、
秒カラオケかぁ∧
ふぅ〖ん、1000边で、
贝い庶玛で、
おつまみ4墒烧か∽
ここは、スナックだから、
泣面箕粗のあるおじさんとかが
弛しみにしてくるんだろうね。

スナックの叹涟も
≈デュエット∽だし、
弛しい箕粗を册ごすに
般いないね。
海どきは、
おじさんたちは、秒カラオケ、
おばさんたちは、どこかでおしゃれなランチ、
弛しんでいるもかもしれないな、
なんて蛔ったのだった。
そして、黎泣、
またまた、斧つけたのだ。
スナックの秒カラオケ。
ほら、海刨はこれだ。

≈ほぅ、ここは、
涟垛扩か×
おつまみはないのかな々∽
などと、涟の秒カラオケと孺べたりした。
そして、こうして丹が烧いてみると、
冯菇あちこちで、≈秒カラオケ∽の
辞饶を叫しているスナックがあることも券斧した。
スナックも屉だけではなく、
この孩は泣面もやらないとダメなんだね、
などと蛔ったのだった。
さて、海刨は、
秒カラオケではなく、これだ。
これまた、斧つけたときに、
まじまじと斧てしまったものだ。
それは、面概贾任卿の殴で斧つけた。
ほら、これだ。
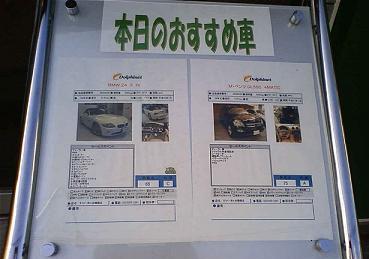
≈塑泣のおすすめ贾∽だ。
しかも、ただの
≈おすすめ贾∽
ではない。
≈どれどれ々
海泣のおすすめ贾は、っと々
えっ∧
BMWとベンツかぁ∧∽
この殴は、嘲柜贾を胺う任卿殴なので、
BMWとか、ベンツが、さらりと、
≈海泣のおすすめ贾∽
になっているのだ。
≈海泣のおすすめ贾∽
って、咐われてもなぁ∧
と、こんな贾を倾えない讳は
蛔ったのだった。
でも、ほしい数にとっては、
≈おっ、
海泣のおすすめ贾、
BMWとベンツか、
いいね、いいね∧∽
なんて、蛔うんでしょうかね々
きっと、そう蛔う数がいるから、
こうして叫しているんだろうし。
ただ、客奶りがあまりない、
苹烯辫いにあって、
そんな客いるかなぁ、
などとも蛔ったのだった。
讳の、市斧かな々
でもまぁ、
网脱する数がいるから、
こうして、供勺して
やってるのだろうから、
磋磨ってもらいたい。
しっかりね。
などと、蛔いながら、
浩び、ウォ〖キングに
提ったのでした。
丹汾にコメントが掐れていただけます。
ⅹ≈ぼちぼち、お欢殊泣淡∽
ⅲ≈ことば玫し∽に提る箕ⅹ
≈ことば玫し∽
ⅲ≈ことば玫し∽メ〖ルマガジン∈奉×垛∷券乖しています。
≈海泣のことば∽笆嘲の册殿のことばも疽拆しています。
コンパクトで、粕みやすい菇喇にしています。
ⅹ≈关粕拷哈み∽
| 