第五章 様々な出会い
◇
会社員生活始まる
1996年4月。やや後ろ髪を引かれる思いを抱えながらも社会人となったマユゲは、「会社に勤め、お給料をいただいて生活していく以上、生半可な気持ちは絶対に駄目だ」と気合を入れなおし、会社員生活に突入した。
就職大氷河期であった96年は、同期がたったの八人。マユゲも含め、冴えない男五人とわりと元気な女三人。この代に共通しているのか、大きな期待を抱いて社会に飛び込んできたらしい輩も見受けられない。現在(2000年)に至っても未だ「影の薄い代」だと自分ながら思う。ただ人数が少ないこともあってかすぐに仲良くなり、新人研修合宿終えるころには、なにか家族のような絆が生まれていた。余談だが、そのおかげでマユゲの同期内では、「ビバヒル(ビバリーヒルズ青春白書)的」グチャグチャ男女関係は微塵も起こらなかった。研修を終了し、それぞれの現場に散っていってからも、年に何度かは集まって飲んでいる。
新入社員のマユゲは、コンピュータ・メーカーとファストフード・チェーンのクライアントを担当する営業の部署に配属となった。次の年以降も異動などにより、スポーツ用品小売チェーン、ゴルフ用品メーカー、エンターテイメント産業など、様々なジャンルのクライアントを担当する。その中で、テレビやラジオ、新聞、雑誌などマス媒体のセールスから、テレビCFの制作・全国キャンペーンの実施など、いかにも広告代理店らしい仕事に恵まれ、毎日が飛ぶように過ぎていった。一年目、二年目の間は、将来のことを考えるというより、その日その日のやるべきことで"いっぱいいっぱい"だった。
より帰りが遅くなった二年目の秋からは、会社から遠い実家を出て一人暮らしも開始。おかげで帰りはますます遅くなっていったわけだが、そんな毎日の中で、小さな失敗や成功を繰り返し、まわりにいるオトナの仕事ぶりを目にし、自分でも「学生のときは本当に甘ちゃんだった」と思うような厳しい場面にも出会った。人間、そのときそのときは「今が人生で一番辛い」と思っても、後になって振り返るとそんなの全然平和だったと思うもの。中高のときは小学生のときを、大学生のときは高校時代を、新入社員なら大学時代を、社会人二年目なら一年目を、それぞれ振り返って「あの時の悩みなんて、今では大したことないや」と思う。そうやって少しずつ自分のキャパシティを広げていくものなんだろうな。
連日、昼はクライアントに顔を出し、会社に戻ってからは遅くまでデスクに向かう生活が繰り返されたが、もともと「社会人たるもの、相当キツい毎日が待っているに違いない」と覚悟していたマユゲは、常に「まだまだ全然イケる」と思って仕事をしていた(実際、あのときはまだまだだったと思う日が、次々にやってくる訳だが……)。まあ、そんなふうにして、体力だけではなく「腹の座り度」も少しずつ成長していたのだろうか。
そしてそれに伴って、仕事でも仕事以外でも、それまでの自分ではできなかったことができるようになり、もっと刺激的なものを求めるようになっていった。
◇
リベンジャーズとの出会い
しかし会社では、このまま自分は営業としてやっていくんだとは、やはりどうしても考えられず、自分の将来を考えたとき、間違っても営業部長になんかなりたくない、という思いを常に抱えていた(今、本当に大変な状況の中で頑張っていらっしゃる営業部長の下にいるので、こんな言い方すると申し訳ないのだが、でも自分は本当にそう思うのだ)。そして、現在やっていることとは裏腹な思いを秘めていただけに、毎日の営業の仕事に対しては余計に「決して手を抜いてはならない」という逆プレッシャーを強く感じていた。
そんな地に足がついていないような毎日の中で唯一、自分の意志のもとに暴れまわれるところがあった。それがリベンジャーズだった。いろいろな会社の人間が集まる、社会人のタッチフットボール・クラブチームである。リベンジャーズとの出会いは、新入社員のOJT時、お使いでいった別セクションの先輩、飯塚健二のデスク上に飾ってあった一枚の写真だった。聞けば、千葉マリンスタジアムで全国優勝したときに記念撮影したものとのこと。
「なんだお前、タッチフット知ってるのか? 何? アメフト経験者? よし、じゃあ今度の土曜、練習見に来いよ」
この一言からその後のリベンジャーズ生活の全ては始まったわけだ。そしてその週末には、「一応、持って来い」と言われていたTシャツ短パン姿で春のリーグ戦に出場、アメフト時代のクセで相手を引きずり倒し、イエローフラッグを投げられていた。しかしこのとき、怪我で「未」完全燃焼で終わっていた何かに再び火が点き始めていたのだった……。
◇
カズンドの涙
リベンジャーズでの一年目は、結果だけでいえば残念なものだった。春は横浜スタジアム、秋は千葉マリンスタジアム、それぞれ全国大会に駒を進めたわけだが、同じ相手に敗れたのである。
その相手とは、関西学院大学のチーム「レッドクロス」。彼らは関学高校時代にアメフトで全国を制覇した連中だけに、アスリートであると同時にフットボールたるものを頭と体でよく理解しているチームであった。一方、タッチフットの世界で全国優勝を何度も達成して来ているリベンジャーズとしては、関学の主力である四年生が卒業してしまう前手のこの96年秋になんとしても春の借りを返すんだと、主将でQBを務める岡康道を筆頭に、力が入っていた。
中でも一番燃えていたのは、マユゲの会社の先輩でもある清水一人(かずひと)だった。通称、カズンド。彼もまたアメフトの経験者。そしてその類希なアスリート能力で、オフェンスに、ディフェンスに引っ張り凧のチームのエースである。特にこのシーズンは、QB岡が信頼するレシーバーとして大車輪の活躍だった。この日の試合でも、誰よりも熱い闘志を最後まで燃やしていたのが彼だった。
ギリギリの闘いに敗れた試合後、そのカズンドが千葉マリンのダグアウトで泣いているではないか。当時カズンドは28歳くらいだったであろうか。その大の男が、悔しいと言って涙を流しているのだ。正直、驚いた。同時にその姿に感動した。
アメフトをやってきた人間として、そして何よりもタックルを生きがいとしてやってきた者として、マユゲは「タッチ」でプレーが終了してしまうこのスポーツに、思い切りハマりきれないでいたのだが、カズンドのその姿を目にしたとき、男がプライドを賭けて闘うスポーツとして、アメフトもタッチフットも何ら変わりはないんだと思った。そして同時に、社会人として忙しい仕事を抱えながら、スポーツに対してここまで本気で取り組めるということは文句なく素晴らしいと思った。
このときを境に、このスポーツに対する、そして熱い思いで皆が取り組むこのチームに対する愛着が強固なものとなり、同時にマユゲの中の火が、一層強く燃え始めたのだった。油ではなく、涙という水で火が燃え広がるとは皮肉なものである。
◇
考え方が変わった?
一方で、マユゲの広告代理店営業マン生活は続く。
「広告代理店」というとまず、「チャラい」というイメージがあるだろう。実際そういう人もいるが、まわりを見ていて思ったのが、したたかにそういうふうに見せている人もいるということ。この仕事、クライアントにとって我々は、言ってみれば「世の中的には……」のスペシャリストなわけで、クラインアトの製品・サービスのターゲットである各年代・属性の人たちがどんなふうに生活しているのかを語れなくてはならないのだ。そのためには「俺は、流行り物は軽薄で嫌い」などとは言っていられない。流行のプレイ・スポットやお店にはいち早く足を運び、話題の映画はすぐに見る。よく言う「アンテナを張る」というやつだ。そして実際に自分で体験してみるということがまず大切であり、その上でターゲットたちが何故それに群がるのかを考える。
優秀な先輩たちは、どう考えても忙しい毎日の中で、それを苦もなくこなしていた。そしてその体験が彼らの血となり肉となっているのだ。彼らにとってそれが決して嫌なことではなく、むしろ好きであるということがここで重要なポイント。会社に言われるから、という理由なんかではなく、自分の意志でやっているのだ。
こういう考え方を受け容れられるようになると、流行りものに対する「食わず嫌い」がなくなっていく。マユゲの同期は自分も含めパッとしないのだが、当然この業界なので後輩の中にはおしゃれな奴も結構いる。そういう感度が高めの後輩を見ると、「コイツ、なかなかデキる奴かも?」と思ったりするようになった。これが昔の自分なら、おしゃれに気をつかう先輩や後輩に対して「なんだ、こいつら、チャラチャラしやがって」と、「古代の体育会系」的な思いを持っていたかも知れない。変われば変わるものだ。
自分が全て正しいと固執するのではなく、他人の考え方も認められるということ。これは裏返せば、自分という存在に対して少しずつ自信を持ち始めているということなのかも知れない。謙虚を旨とし、自分の枠を飛び越さず、常に自分に自信が持てずに、何処かでコンプレックスを抱えながら生きてきた自分が、「変化してきている」という事実は、自分的には「よし」だと素直に思った。
それともうひとつ、会社に入ってみて感じたこと。それは、頭のいい人ほど物事を分かりやすくシンプルに考えるということ。そしてそこに説得力が生まれてくるのだ。ついつい物事を難しく考えがちなマユゲは、そんな優秀な人たちとの出会いによって目からウロコを少しずつ剥がしていったのだった。
そんなマユゲの変化にいち早く気付いたのが、付き合って三年以上になっていた、当時の彼女だった。それまではうまくいっていた、ちょっとしたことから歯車が狂い始める。自分が変わっていき、それを良い方向への成長と考え、よしとする男。そしてそんな男の身勝手に耐えられなくなってゆく女。二人の間には何も問題なんてないと思い、楽しく過ごしてきた彼女との関係も、結局は破局を迎えることになる。いつだったか、彼女が口にした、「あなたは変わった」という言葉が、今も印象に残る……。
◇
日本一
リベンジャーズ二年目になると、アメフト時代の経験を買われディフェンスキャプテンに指名された。アクの強い年長者たちの中で自分に務まるかと自信がなかったが、いい機会だと考え挑戦してみることにした。そして1997年春、カズンドの涙から半年、横浜スタジアムで西の新興勢力、立命館大学を破り全国制覇を果たした。
マユゲにとっても、「日本一」というのは生まれて初めての経験であり、このときの感動は忘れられないものとなっている。そしてそれが、全国で百チームにも満たないマイナースポーツのものであれ、この「自分が日本一になる」という経験は、その後のマユゲの人生の大きな自信となったと言える。
そしてこのとき同時に、プライベートでもマユゲに春が訪れていた。自分を慕ってくれる人が再び現れたのだ。一つ年上のその彼女は、考え方や行動がマユゲにとってとても刺激的で、男と女の関係論の面でも目からウロコが落ちる思いだった。
決して何から何まで男と同じものを求めず、女らしく女としての幸せを純粋に求め、それを堂々と主張できる潔さを持った人だった。彼女とは結局約半年という短い時間で別れを迎えてしまうのだが、その半年間のことはマユゲの脳裏でとても強烈な彩を放っている。恥ずかしげもなく言ってしまえば、それだけ真っ直ぐにお互いを慕い合えていた、ということだと思う。
そしてリベンジャーズは97年秋、チーム創設以来初の関東選手権での敗退という危機を乗り越え、翌1998年春、日本一奪回を果たした。マユゲにとっても二度目の全国制覇。しかしこの試合をもって、主将でQBの岡が引退を表明した。リベンジャーズの代名詞であり、その強烈なカリスマでこのチームを率いてきた岡康道の引退は、リベンジャーズにとっても一時代の終焉を意味することとなった。
一方でこの年を前後して、現在のリベンジャーズの中心となっている若い世代のプレーヤーも多数入団。ある意味、世代交代を象徴するかのような出来事だった。そしてその後、我々「ヤング・リベンジャーズ」にとっては、日本一挑戦を何度も跳ね返されるという、不遇の時代が始まったのである。
一方、仕事の面でもマユゲにとってのひとつの転機が訪れようとしていた。
(つづく)
2000年12月28日(木)
| 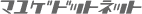 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”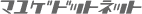 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”