第四章 学生(コドモ)から社会人(オトナ)へ
◇
神様と暮らす人々
間違いなく日本とは違う常識が支配するインドの日常。そこに身を投じることの衝撃。そして固定観念からの解放。そんな、この旅行の醍醐味とも言える感覚を徐々に味わいながら、夜行列車の二等寝台でインド人と一緒に揺られること数時間、マユゲたちは、明け方のヴァーラナーシーに到着。
この街はヒンドゥ教の聖地。インド各地から巡礼の人たちが集まってくる場所なのだ。彼らは、この街を流れる聖なる大河ガンガー(ガンジス川)のほとりにある、「ガート」と呼ばれる沐浴場に早朝から集い、それぞれ思い思いに神への祈りを捧げ、そして聖なる水をその体に浴びる。それを最大の喜びとして生きているのだ。
ガートからはダサーシュワメードロードと呼ばれるメインストリートが街の中心に向かって伸びる。メインストリートと言っても、土埃が舞い、其処此処に牛の糞が落ちているような汚い道なのだが。このあたり一帯がいわゆるバザールとなっていて、道を挟むように定食屋(ターリと呼ばれるインド風定食が食べられる)、ゲストハウス等の店が軒を連ねる。そこからはさらに細い路地が迷路のように伸びていて、そこにもまた店があるのだ。
この路地を歩くのが結構面白い。薄暗く、人がやっとすれ違える程度の細々とした道。衣料を売る店があると思えば、その隣は生鮮食料品の店。さらにその隣ではオヤジが髪を切ってもらっている。その次は店ではなく普通の民家。開けっぴろげな窓からは昼寝を決め込むオバちゃんの姿が。そしてまた店が続く……といったような、なんとも無秩序なレイアウト。
マユゲが店に気をとられつつ歩いていたとき、誰かと肩がぶつかった。反射的に「Oh,sorry...」と謝りながら振り向く。するとそこにいたのは、なんと牛。そう、ヒンドゥ教においては、牛は「神」であり、人間と交じって堂々と街中を闊歩しているのだ。どうりで道中に糞が多いわけだ。なるほどね、と変なところで納得してしまった。
このとき以外にも事件はあった。バイク型リキシャに乗って、ある程度広い大通りを走っているときのこと。インドも日本と同じ左側通行。なんてことはないポイントで何故か渋滞が始まる。まわりの渋滞慣れしていないインドの運転手たちは、即行キレて右に膨らみつつ追い越しをかけ始める。これにまた皆がどんどん続いていっちゃうもんだから大変。同じ方向を向いた車両だけで、対向車線までの道全体をふさいでしまうかたちになってしまった。反対側から来る車が鳴らすクラクションと、それにまた応戦する逆ギレクラクションで、プープー、パーパーと、街はもう大パニック。30分かけてようやくそれが解消され、渋滞の先頭に達したとき、そういうことかと、これまた納得してしまった。そう、このときも道のど真ん中に在らせられたのは、牛の親子。うららかな二月の陽光を浴びて気持ちよさそうにお昼寝していたのだった……。
◇
神様に召された老人と神様を売る少年
ヴァーラナーシー何日目かのこと。ガート付近の道端におじいさんがうつ伏せに倒れていた。おいおい大丈夫かよ、と思いながら近づいてみると、顔を横に向けた彼の鼻の穴から、何匹かの蝿が出てきては飛んでいくではないか。どうやら、聖地を目指し辿り着いたものの力尽きた、敬虔な巡礼者の最期であったらしい。こんなにリアルな死体を見たのはほとんど初めての経験であったマユゲは、激しく動揺した。そしてその死体なんて全く目に入らないかのように平気で横を行き交うこの街の人々にまたショックを受けた。ここではきっとよくあることなのだろう。翌日同じ場所に行ってみると、そこにはもうおじいさんの姿はなかった。しかるべき人がしかるべき処理をし、また何ごともなかったかのように日常が繰り返されるのだ。
また別の日。ガート近くを歩いていると、ひとりの少年が声をかけてきた。小学校高学年くらいだろうか。始めは何を言っているのか分からなかったが、よく聞いてみると日本語ではないか。「カミサマ、カウカ?カミサマ、カウカ?」。手にもっているのは、日本でいう七福神のような、何種類かのインドの神様の小さな人形たちだった。どうやら自分で木を彫って色付けしたらしい。マユゲたちを日本人と見るや商売を持ちかけてきたのだ。「神様は買わないよ」と言って断るものの、向こうも生活の糧がかかっているのか、必死に食い下がってくる。旅行者たちと交渉するうちに身につけたのだろう、日本語・英語が入り混じってはいるものの立派にコミュニケーションが成立する言語を話す。正直、恐れ入った。しかし、悪いがそれとこれとは別。神様は買わないよ。
歩き続けるマユゲに必死について来ていた少年も、30分ほど粘ったもののさすがにあきらめたようだ。すると今度はこっちがすまない気分になってしまう。代わりに、というわけではないが、ガンガーの手漕ぎボートに誘った。商売の関係がなくなった少年とマユゲは、ボートの上でしばし歓談。その時計はジャパン製か?その靴は?そのサングラス、かけさせてくれない?好奇心旺盛な少年、マユゲの身につけているものが気になってしょうがないらしい。そこで、少年にサングラスをかけさせて船上で記念撮影。思い出の一枚だ。
その後、ガンガーの向こう岸まで行ってみようかと誘ったが、どうやら対岸はここの人たちの間では「死の世界」と考えられているらしく、断られた。その国の文化を知らないと、悪気はなくとも現地の人にとってはとんでもないことをしてしまいがちなんだな、と少年から教えられるマユゲであった……。
◇
死を待つ家
ヴァーラナーシー、またまた別の日。この街にあるという「死を待つ家」に行ってみることにした。聖地で安らかに神に召されることを願って余生を過ごす、おじいさんやおばあさんたちが住まう家――。
死ぬために集まる家。まずそれだけでショックである。そしてガンガー沿いにあるその家の真横は火葬場となっており、「生を全うした者」から順々に焼かれていくのだ。白い布で巻かれた人型の物体が運び込まれては煙となっていく。それが休みなく目の前で行われているのだ。もう、言葉が出なかった。宗教というものに身を捧げ、あるものを信じ、そのリズムの中で生きていくことはその人の自由だと思うが、どんな生き方を選ぶせよ、いつか死んでいくときには皆同じように骨となり、同じように大地に帰ってゆくのね……。
聞くところによると、何らかの理由で指が一本ないとか、成人せずに死んでしまった赤ちゃんとか、「生を全うした」とみなされない者は、ここでは焼いてもらえないらしい。焼かれずにガンガーに流されるのだ。のんきにボートを漕いでいた我々旅行者の横を流れていたかもしれない、と思うと背筋がゾッとした。また、インドには未だにカースト制度の名残がいまだあると聞く。低いカーストの者もまた、このような立派な火葬場では焼いてもらえないとのこと。
このカースト制度といい、南アの人種差別といい、日本の部落差別といい、映画「ミシシッピー・バーニング」のアメリカ南部といい……、人間というのは自分より弱い立場の者を無理矢理にでもつくらないと怖くてしょうがないらしい。日本のガキどもの「いじめ」問題の心理も、きっとそういうことなんだろう。これに限らず、人間にはそういう「弱い」面が生まれ持ってある。これは神様が敢えて人間を不完全に造ったんだろうから、きっとしょうがないんだろう。でも、「それじゃダメなんだ」と、いい方向に努力できるのもまた、人間が与えられた能力。自分はどうだ?その能力を生かせているのか???
次々に焼かれていく人々、そしてその横で無邪気にクリケットに興じるインドの子供たち、という強烈な対比の場面を目にし、動くこともままならなくなってしまったマユゲ、長い間その風景の中で考え込んでしまうのであった……。
◇
混沌の街
ヴァーラナーシーを発ち、今回のインド紀行最後の都市カルカッタへ。英国調の大建造物やそれなりに整備された大通りなど、植民地時代の名残を色濃く残す街。しかしそのインフラ的なものとは対照的なほど、そこに住まう人々の「生活臭」が最も強烈に感じられる街。一連の旅のなかでも、最も強烈な「カオス」がそこにはあった。
何処へ行っても、とにかく人が多い。そして一歩路地に入れば、道端でただ手を差し出し、その日の糧とするためのバクシーシ(施し)を求める不具の男たちがごろごろ。そして幼い弟を連れ、我々旅行者を見つけると片っ端から手を差し出しながら見上げてくる少女も。かと思えば、レストランではきちんとした身なりのインド人の家族が割と豪勢なディナーを楽しんでいる。最下層の人からトップカーストの者までがごっちゃになって生活しているのだ。新宿西口のビジネスマンとホームレスどころではない。その差がもっともっと強烈なのだ。日本と何ら変わらないような場面と、そのすぐ隣にある信じられないような正反対の場面。そのギャップはすぐには消化しきれるものではなく、インド旅行の初心者はカルカッタではなく、まずデリーから入国するのが無難といわれるのが分かる気がした。
そんなカルカッタでのこと。メーターのないタクシーで、例によって事前の料金交渉。たまたま経済力のある国に生まれたからといって何でもかんでも金をばらまけばいいというものではない。労働とそれに対する正当な対価。これは大切にしなければ。ガイドブックの情報と、これまでの行程での体験でだいたいの相場感は身についている。勝負は開始された。
運ちゃんに目的地を告げると、
「そこまでなら50Rs(ルピー)だ」とふっかけてくる。これはもう挨拶のようなもの。
「うっそ言え、高いよ。25Rsでしょ?」と半額でこちらも"挨拶"を返せば、
「いや、せめて40Rsですな」
「じゃあ、いい。バスで行く」
「あーいや待った!35Rsでどうだ?」
「30Rs!」
そこで運ちゃんも折れる。頭をちょっとだけ横にかしげるインド特有の「OK」のサイン。
「いいね、30Rsしか払わないよ」
「OK、30Rs」
一応、念押しし乗り込むものの、これでも戦いは終わらない。目的地に着いてみると40Rsよこせと言う。事前交渉どおりでない金額を請求されたのは初めてであったマユゲ、真剣にキレてしまった。怒り顔で、
「30Rsって言ったよな? あん?」
「でも道が混んでたから・・・・・40Rs」
「どこがじゃ、コラ。全然空いとったやないかい!」
さすがに関西弁ではなかったが、熱くなって応戦する。しかしさすがは非暴力主義を貫いたマハトマ・ガンジーの国。運ちゃんは腰の銃を抜いてズドン、というアメリカのような反応ではなく、一応言ってみただけだったのか、すまなそうな顔で、
「OK、30Rs」
こうなると今度はこっちが悪いことしたようで、「ごめん。俺も言い過ぎたよ」という気分になってしまった。温室育ちで世間知らずの東方の小僧を、こういうかたちで諭すとは、さすがはガンジーの国。おそるべし、インド魂。
そして、ここカルカッタでそんな「生活臭」や「インド魂」に触れたマユゲたちも、いよいよ帰国のときを迎えたのであった……。
◇
卒業
この旅を通してマユゲの頭の根っこの部分に、ある思いが芽生え始めていた。
日本で通用している価値観だけが全てではない。何を大切と思うかは、自分で見つけるべきもの……。そしてそう思ってしまったのが、他でもなく、日本における価値観を疑うことが必要とされない(むしろそう考え実行に移すことが即ちドロップアウトを意味する)、「ニッポンのサラリーマン」としての生活を始める直前のことであったのだ。
就職を考えたときには、「自分には別に世界志向なんてないし、世界を股にかけるビジネスマンなんて興味なし」と思っていたのだが、『世界』というのはそんなに一面的なものではなかった。知らずにほざいていただけだったと、今になって思う。いろいろな物や人、暮らし、考え方、宗教観など様々なものを見、体験して初めて、自分は何者なのか、そして何をしたいと思うのかが見つかってくるものなのだろう。今はそう思う。当時のマユゲの頭の片隅にも、きっとそんな思いが生まれ始めていたのではないかと思う。少しずつ自分が変わり始めていたのだ。
帰国後、卒業試験はほぼ全てパス、結果として四年間のうちで最多単位を取得というかたちで、無事「卒業」という運びになった。卒業式の日も、それからの未来に思いを巡らすというよりもむしろ、「本当にもう卒業なの?」というやや後ろ向きな思いを抱えつつ学長の送辞を聞いたのを覚えている。
そして1996年4月、後ろ髪を引かれながらも、マユゲの会社員生活が始まることとなった。
(つづく)
2000年12月27日(水)
| 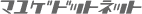 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”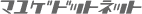 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”