第三章 マユゲ、新世界を踏む
◇
「未」完全燃焼
マユゲ大学四年、アメリカンフットボール生活最後の1995年秋リーグ戦。会心のスタート、突然の負傷と絶望、そして復帰・・・といったいくつかのドラマを乗越え、マユゲも宿敵K大との優勝を賭けたリーグ最終戦のサイドラインに裏方として立つ。
前半は味方のペースで折り返したものの、後半が開始されてしばらく、試合に変化があった。それまでギリギリのところで緊張感を保ち、相手強力ラインのブロックに対しなんとか持ちこたえたていた味方ディフェンスのフロント勢にも疲れの色が見えはじめていたときだった。敵の大型ランニングバックがブロックで空いた穴をすり抜けて走り出る。セカンダリーの対応にも遅れがあった。ボールを持った敵ランニングバックは、フィールドの左側を駆け上がり、エンドゾーンに迫る。逆サイドのコーナーバック佐藤がギリギリの所で止めるも、その後のランプレーで中央付近を押し込まれ、タッチダウンを許してしまう。
ここを境とするように勢いが相手に移った。再びモメンタムを引き戻したい味方オフェンスにも、焦りからミスが生まれる。投げ急いだパスをインターセプトされてしまう。その後逆転のタッチダウンを奪われた我々は、終了間際に最後の反撃を試みるものの、再度インターセプトを喫し万事休す。すべてを賭けた試合で、敗れた。
マユゲのポジションを引き継いだ後輩は、ただただ謝りながら泣いていた。サイドラインに立って見ることしかできなかったマユゲは、確かにやりきれない思いではあったものの、意外にも静かな心境だった。フィールドで闘った四年生も概ね、悔しさとともにすがすがしさをその表情にたたえているように見えた。
こうして、マユゲが高校時代から生活の第一においてきたアメリカンフットボールは、終わった。
◇
インド人、ウソつかない?
残りの学生生活といえば、卒業試験と卒業旅行。この四年後期の試験は、生まれて以来一番しっかり勉強した、といえるほど準備をした。それは単に、就職が決まっていて尻に火が点いていたから、だけのことであったのだが。そしてその結果がでるまでの二週間、卒業旅行に出る。
行き先はタイ、インド。小学校四年生の夏休みにサマースクールでスイスに行かせてもらったとき以来の海外旅行。はじめは、アフリカのサバンナで野生動物でも見ようかなとも思っていたのだが、当時アフリカでは「エボラ出血熱」という奇病が流行しており、同じ大学の学生で命を失った者も出たということもあり、行き先をインドに変更したのだった。ヨーロッパやアメリカは全く候補に入らなかった。日本と同じような文明国には興味を感じなかったのだ。今だからこそ行ける、発展途上の別世界に身を投じたかった。
バンコクのカオサンストリートでデリー行のエアチケットをとったものの、一番早くて四日後。その結果、計画ではインドの帰りに寄るはずだったリゾート地プーケットに先に行くこととなる、などのハプニングもあった。
プーケットでのビーチリゾートを満喫、象にも乗ってゴキゲンのマユゲたち一行は、バンコクからデリーに乗り込む。まず、空港内で警官が気の弱そうなインド人を捕まえてカツアゲしているのには驚いた。
空港内でデリー駅までのタクシーを手配、乗り込むと連れて行かれたのは何やら怪しい事務所。中にいたボスが言うには、「デリーからアーグラーまでの列車は今日はもう終わり。俺が宿を手配するからそこに泊まれ」とのこと。ガイドブックにある時刻表によれば、まだ列車はあるはず。明らかに怪しいと察知した我々は、事務所を飛び出し街中へ逃げる。
そこは、なんのことはない、デリー駅の裏だった。助かったと思って切符を買おうとすると、今度はインド人が群がってくる。皆、同じように浅黒く焼けた顔、鼻の下にはひげ、そして人を圧倒するような大きな瞳。「何処に行くんだい?俺が手配するよ」。皆、口々に同じようなことを言う。もう誰を信じていいのか分からない。ややパニック状態のマユゲ、「もう放っといてくれ。自分で手配する。いいかい?」と人差し指を立てる。しかし窓口の列に並んでも、まだ寄ってくる。マユゲの番が来てやっと切符を買い、仲間のものと見比べるとどうやら違う種類。仲間は断りきれずあるインド人に頼んだらしい。それは貨物車のチケットだった。
間違えられたチケットを窓口で取り替え、冷たいものでも飲もうと駅近くのダウンタウンをうろつく。汚い。とにかくあちこちがゴミの山。対インド人のストレスと、街の汚さ、そして照り付ける陽の暑さもあり、刺々しい精神状態となったマユゲは、インド到着初日にして「こんな国、二度と来るもんか」と真剣に思った。
◇
自分の胸に手を当ててみよう
その日のうちに、タージマハールで有名な街、アーグラーに入る。ここで泊まったホテルでまた軽いハプニング。
同部屋の仲間がシャワーを浴びているバスルームから悲鳴が聞こえる。何が起こったかと思い覗いてみる。シャワーが水しかでないのは、タイでもそうだった。安宿だから仕方ないよ。「いや、違うんだ。なんか、しびれるんだよ、このシャワー」。どうやら漏電しているらしかった……。
翌朝早く目が覚めてしまったマユゲ、地階に降りてホテルの前庭に出てみる。インドといえども、ここは北部で、時は二月。朝はそれなりに冷え込む。庭の端に座り一服していると、ホテルの主(あるじ)がゆっくりと歩いて来て横に座る。「おはよう。結構寒いんだね」のようなことをきっかけに少しおしゃべりをする。すると主は使用人を呼んで何やら話しかけた。ヒンドゥ語らしくマユゲには分からない。主は物静かで口数のすくない男だったが、その話し振りから決して悪い人ではないことが伺えた。
しばらくするとさっきの使用人が両手に湯気が立ち上るカップを持って帰ってきた。「チャイだよ。飲むかい?」。主の粋なサービスだった。マユゲが日本から来たというと、このホテルにはかつても日本人が泊まったことがあるらしく、喜んで宿帳を持って来て見せてくれた。デリーではインド人に対して片っ端から「こいつらは俺をだまそうとしている」と思ってしまっていたが、こうして落ち着いてみると、「駅で寄ってきた奴らのほとんどは、親切心からだったのかも知れないな」とも思える。昨日の自分を少し恥ずかしく思った。
◇
インドに入りては……
チェックアウトし主に別れを告げた後は、名所を見て回る。夜には次の都市ヴァーラナーシーへ向かう予定だ。
ヴァーラナーシー行の列車に乗る駅までは約20キロほど離れている。バスターミナルで運転手たちに尋ねてまわるも、皆、首を横に振るばかり。時計をみると列車の発車時刻は刻一刻と迫る。そこで、リキシャ(人力車。50ccバイクの後ろに二〜三人乗れるよう改造したタイプもある)の運転手をつかまえ、地図を片手に「この駅まで、○時○分までに行けるか」と尋ねる。こちらの慌てようが分からない運転手は、あっさりOKと答える。ホントに大丈夫か?とは思ったが、この男に賭けてみることにした。
真っ暗なインドの国道。照明はほとんどなく、リキシャに申し訳程度でついているヘッドランプが照らすところ以外は全く見えない。エンジンの音からすると全開で走っているらしい。しかし遅い。時折、物凄い音量でクラクションを鳴らしながらトラックが追い抜いていく。インドの大型車には大抵「目」がついている。車体の前面を顔になぞらえて、「目」をペイントするのだ。追い抜いていったトラックには、象の鼻まで書いてあった。なんとかっていう神様だな、この象は。
しばらくすると、エンジン全開で走っていたリキシャのスピードが突然落ちた。どうしたのかと思っていると……、
「ガタン」
道路にある舗装の継ぎ目が出っ張っているのだ。運転手はまたスピードを上げる。おいおい、いちいちいいよー。そのくらいの衝撃我慢するよー。のんびり屋でおとなしそうな運転手もそこは譲らない。彼等にしてみれば大事な商売道具であるタイヤと車体を守らなければならないのだ。
次第にマユゲたちも、これで間に合わなくったとしてもいいや、と思えるようになった。こうして、夜風吹くインドの闇の中を、今日初めて会ったインド人が運転するポンコツに乗ってぶっ飛ばしている。これが面白いんじゃない。列車なんて明日だってあるさ。間に合わなかったら駅で寝ればいいさ。そう思った。
そして駅に無事到着。結局一時間以上走っただろうか。時計を見るとギリギリ間に合いそうだった。運転手に料金を支払い、礼を言ってホームへ急ぐ。列車はいなかった。駄目だったか。仕方ないなと思いながら駅員に尋ねると、まだ到着もしていないと言うではないか。列車は結局は30分ちかく遅れて到着。世界一正確と言われる日本の電車に慣れているだけに、インド国鉄のオトコ前ぶりにはビックリしたものだ。
列車に乗り込み、チケットを見ながら自分達の寝台を探す。確かにマユゲの席であるはずの、一番上の寝台にはすでにインド人が七人くらい折り重なるように乗っていた。もうこれぐらいでは驚かない。そこは自分の席であることを主張すると、意外にすんなり三々五々散っていった。まったくまいるよな、と思いながら寝台によじ登り、バックパックをチェーンで手摺に巻きつけて枕がわりにする。ふと横を見ると、向かいの寝台はムスリムの二人連れ。ターバンを巻いたひげ男だ。軽く目で挨拶だけして、マユゲは横になり、眠るために目を閉じる。
しばらくして、うつらうつらした状態のときに足元になにか邪魔なものが当たるのに気付く。目をこすりながら起き上がると、なんとさっき散っていったうちの三人が戻って来てマユゲの足元に座っているではないか。これにはさすがに驚いた。一瞬、怒ろうかと思ったが、でも座れるんだからいいか、と思いなおし放っておいた。そして自分の足元にインド人が腰掛ける寝台でマユゲは眠りについた。
徐々に日本にいるときの価値観から解き放たれるのが心地よくなってきていた――。
(つづく)
2000年12月22日(金)
| 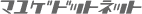 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”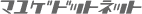 diary/column “mayuge の視点”
diary/column “mayuge の視点”